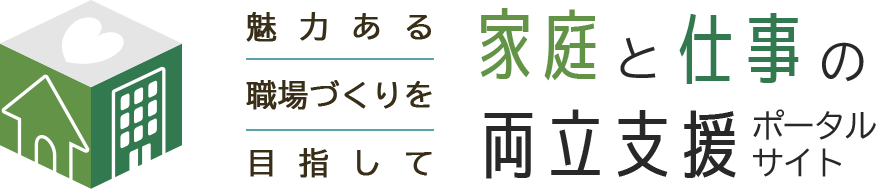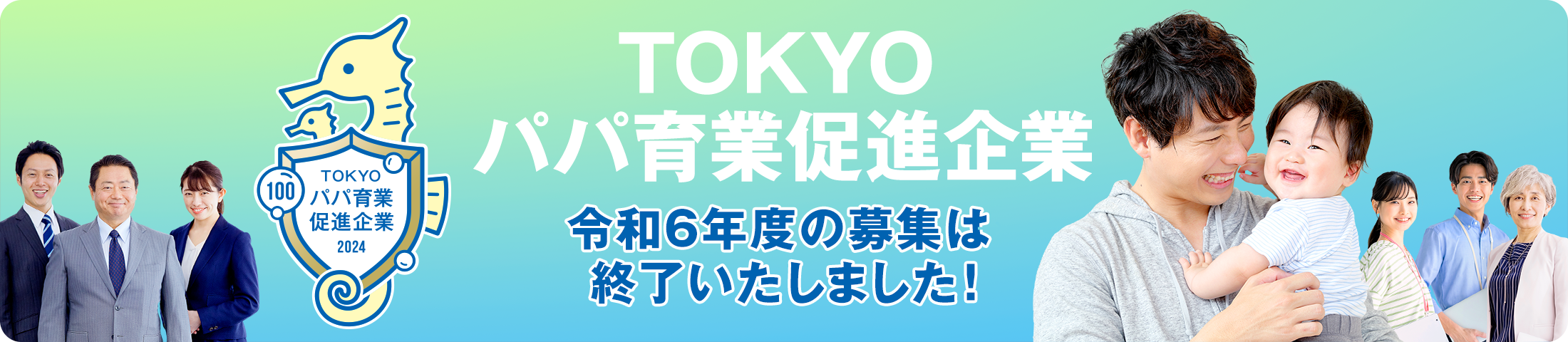「楽しく勝てる企業」への道のりが
パパ育業推進の土壌を耕す

お話を伺った人
経営者・人事労務担当
イーソル株式会社
代表取締役社長
長谷川 勝敏さん
イーソル株式会社
管理統括部人事部・人事部長
澤田 綾子さん
従業員
イーソル株式会社
ソフトウェア事業部エンジニアリング本部アプリケーション開発部Entertainment
荒岡 克史さん
IoTのリーディングカンパニーとして、自動車、ロボット、VRをはじめとしたエンターテインメントなど幅広い分野における革新的技術の提供を通し、より快適で安全なコネクテッド社会の実現をめざすイーソル株式会社。世間の動きに先駆けて従来型の働き方を見直し、「労働時間の長さではなく、時間内でどれだけ高い成果を挙げられるか」を重視する「楽しい“働き方”チャレンジ」プロジェクトを始動させることで、パパ育業の推進にも成功しています。出産・育児に限らず、介護など、さまざまなライフイベントと仕事の両立支援により、レジリエンスの高いサステイナブルな組織をめざす同社の取り組みを、詳しく伺いました。
イーソルの3つのポイント
- 1.トップが「男性育休100%宣言」を早期に行い、「取得して当然」という姿勢を社内外に周知。
- 2.「楽しく勝てる企業」への道のりが、自然とパパ育業推進の土壌を築く結果に。
- 3.ガイドブック制作やセミナー開催、個別面談・特別休暇の設定など、道筋の各所で具体的サポートを提供。
経営者・管理職インタビュー
INTERVIEW 01_代表取締役社長 長谷川 勝敏さん
伝統的な働き方への疑問から、新しいチャレンジがスタート
男性育児休業おいて2021年75.0%、2022年83.3%、2023年66.7%と高い取得率を誇り、比較的長期の取得も多いなど、パパ育業推進において確かな成果を挙げているイーソル。しかし、これは単独の取り組みではなく、幅広く働き方の見直しに取り組むなかで自然と得られた成果だと長谷川社長は強調する。
「2025年に50周年を迎える弊社では、以前は昔ながらのソフトウェア会社気質が残る側面がありました。タイトな納期や顧客の期待に応えるためには、残業や休日出勤もやむなしという社風があったのです。しかし、1982年の入社以来エンジニアとして歩み、管理職、役員も経験するなかで、私自身はこの社風に強い違和感を抱いてきました。どんなに効率よく成果を挙げても長時間働いた人の方が評価されるのでは、やる気を失ってしまいます。そこで、代表取締役社長就任の前年の2012年に、『楽しい“働き方”チャレンジ』プロジェクトをスタートさせたのです」
世間の動きに先行して働き方改革に着手した長谷川社長は、「どれだけ長く働くかより、時間内で高い成果を挙げることが重要」という考え方を社内に浸透させるべく、トップとして強いメッセージを発信。現場で指揮する管理職や社員と積極的にコミュニケーションをとったそうだ。
「水曜と月末の金曜はノー残業デー、それ以外の曜日も残業は20時までといった目標を立てて、トップである私から発信。同時に、毎始業時にそれぞれの1日の予定を共有し、就業前にその進捗を振り返るといったプロジェクトチーム内での情報共有の機会も増やすように促しました。最初はある程度の反発もありましたが、いざやってみるとできるという実感に触れるうち、そうした声もなくなりました。取り組みの成果を一過性としないため、出産・育児、介護といったライフイベントと仕事の両立を支援する、多様な働き方・休み方のための各種制度も整備。それぞれの活用を進める取り組みの一つとして、男性の育児休業推進にも乗り出したのです」

「楽しく勝てる企業」であるために、パパ育業は必要
「10年以上連続100%を達成した女性の育休取得と復帰後の定着は順調に進んだものの、男性の育休についてはその必要性が十分に認知されているとはいえない状況でした。そこで、2016年にトップメッセージとして男性の育児休業推進に対しての考え方を明確に打ち出しました。近い将来に労働人口減少が見えているなかで、育児や介護などで時間的制約を持つ社員がいきいきと働き続けられないことは会社として大きな損失である点、ワークライフバランスを実現することによる自身の健康と家庭の安定が、個々の業務推進における力になる点、そして男性育休推進の取り組みが業務の効率化にもつながる点などをまとめた内容です。男性育休を含む働き方改革を進めることこそ、『楽しく勝てる企業』をめざすうえで欠かせない施策であることを改めて強調した形です」
早期から改革に取り組んできた土壌もあり、大きな課題や阻害要因に阻まれることなく取り組みは進み、パパ育業でも冒頭に挙げた成果につながったそうだ。
「国内においてエンジニア不足が叫ばれていますが、弊社のようなソフトウェア会社にとってエンジニアは資本。まさに『人財』です。男性育休推進を含む『楽しい“働き方”チャレンジ』により、社員に中長期にわたって安定的に活躍してもらうことは、経営に直結する課題を解決するために必要なことだと考えています」
最後に、長谷川社長個人のパパ育業への考え方を問うと、笑顔とともにこうした答えが返ってきた。
「父親として子ども2人をすでに社会に出した身ですが、男性の育児休業などとんでもないという時代に子育てを任せきりにしてしまった妻には、いまだに苦言を呈されることも。1日でも1週間でも良いから育児に取り組むことが、将来の家庭や夫婦関係にも大きな影響を与えると思いますよ(笑)」
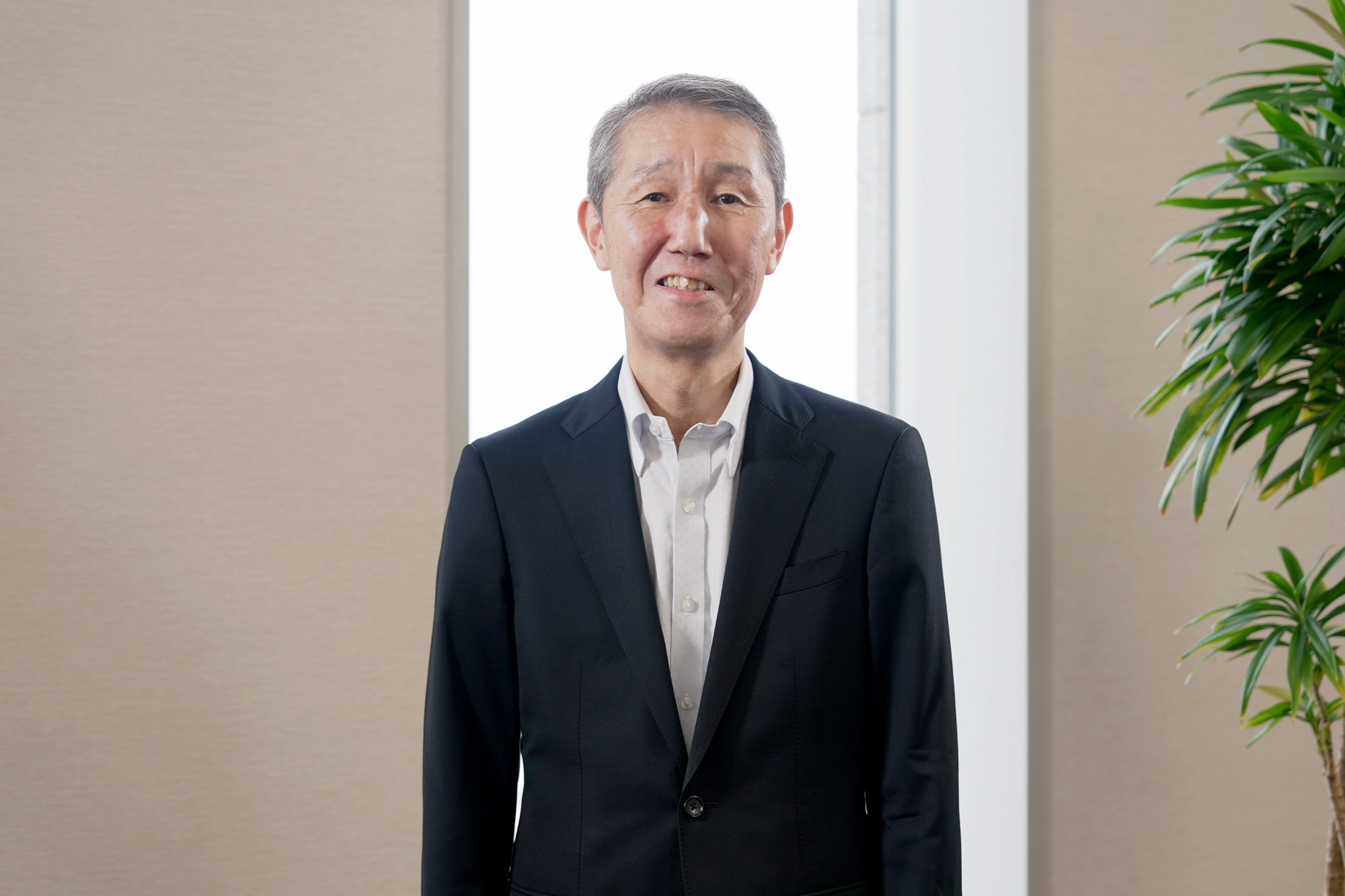
INTERVIEW 02_管理統括部人事部・人事部長 澤田 綾子さん
明確なトップメッセージを、いつでも参照できる形で公開
管理統括部人事部・人事部長としてパパ育業推進にも取り組む澤田部長。ソフトウェアエンジニアとして活躍後、管理職を経て15年ほど前に管理部門に異動した当初は、人材開発・育成に力を入れたいという経営者の意向を受けていたという。
「管理職として人材開発・育成の重要性は痛感。強い組織にするために欠かせないものとして人材育成体系の整備やキャリア開発支援などを進めていくうち、働き方を見直すことの必要性・重要性に気づいたのです。どんなに良い人材を育てても、一人ひとりがより良いコンディションで意欲高く働き続けるための環境がなければ、期待通りの活躍は望めません。そこで、経営陣にそうした旨を進言し、『楽しい“働き方”チャレンジ』プロジェクトがスタートすることとなりました。そのなかで、従業員満足度・企業価値・採用力向上の観点から、男性育休の推進も早期に提案したのです。」
トップも巻き込んでのプロジェクトを推進するうえで、澤田部長が最も大きな効果を感じたのは、メッセージの明確化だったという。
「トップが明確にメッセージを発信したことで、会社として推進していることが一部の層向けではなく、全社員に向けた取り組みであることが強力に伝わりました。男性の育休取得における意思表示のハードルもグッと下り、管理職や同僚の受け止めも好意的なものになったのです。その一因としては、『楽しい“働き方”チャレンジ』プロジェクト初期からの取り組みで、多様な働き方・休み方を受け入れる土壌が整っていたこともあるでしょう。エンジニアたちがプロジェクト単位で動くことが多い、弊社の業務体制が制度にマッチしていたこともあります。制度活用のノウハウを具体化するためには、制作したガイドブックを社内サイトに掲載。制度の概要とトップのメッセージを、全社員がいつでも参照できるようにしました」

100%に拘るより、個々に寄り添い選択をサポート
管理職と当事者双方に向けた情報をまとめたガイドブック公開に加え、パパ育業についての社内セミナーも開催。また、育休申請から育休中、復帰前後の各段階におけるサポートも強化したそうだ。
「事前に予定を把握するきっかけになればと、配偶者に出産予定がある場合に取得できる特別休暇を設けたほか、育休開始前後には個別の面談も実施しています。休業を取得する時期や分割の仕方など、本人のみで検討するのが困難なことに対しては個々の事情に応じたアドバイスも可能です。2022年の法改正以降、状況を見ながら複数回取得するケースも増えており、相談内容はさらに複雑化しています。そうした相談への対応には、今後も力を注いでいく予定です」
きめ細やかな支援でパパ育業推進に取り組んできた澤田部長。自身の育児休業から復帰した際の経験も役に立っているという。
「復帰後は定時で仕事を切り上げざるを得ず、自由に時間が調整できる前提での働き方を見直す必要がありました。時間に制限があるなかで、いかに成果を挙げるかといった、まさに『楽しい“働き方”チャレンジ』のベースとなる視点が求められるのです。育休をきっかけに業務の棚卸がなされ、その後の遂行が効率化されるといった効果も見られています。また、女性の育休取得では10年以上連続100%を達成しており、当たり前に現場に復帰して活躍する姿が、管理職を中心とする社内の意識を変えてきたともいえます。これから社会で活躍する次世代にとって、働くことは必ずしも人生の中心ではなく、仕事に人生のすべてを捧げる必要はないという、ある意味人間らしい考え方も増えてきていると感じます。取得率100%だけに拘るのではなく、それぞれの想いに寄り添い、一人ひとりが納得してベストな選択を下せるよう、サポートしていきたいと考えています」

従業員インタビュー
INTERVIEW 03_従業員 荒岡 克史さん
制度上の疑問や不安は、個別面談で解消
2018年の入社後、ソフトウェアエンジニアとして多様なアプリケーションの開発などに取り組んできた荒岡さん。第一子の誕生に合わせ、2023年9月末から2024年1月上旬までのおよそ3ヶ月間、パパ育業に入ったという。
「入社時の説明や資料にもありましたし、入社後にも全社メールや社内ポータルサイトでの発信により、会社としてパパ育業を推進していることは感じていました。出産から子どもが小さい間だけでも父親として育児に専念したいと考え、いずれ子どもが生まれるようなことがあればぜひ制度を活用したいと思っていたのです。そんななかで、配偶者の妊娠が判明。まずは直属の上長である課長に相談し、『おめでとう!』の第一声とともに受け入れられました」
はじめてのことであり、多少の不安はあったものの、相談を受けた上司は素直に喜びを表現。すぐに育休取得の意向を人事担当者へと伝えてくれたという。
「早めに相談したことで、業務の引き継ぎ準備も時間をかけて行え、欠員の補充も受けられました。プライベートを含めて個を尊重する空気感のおかげでしょうか、プロジェクトチームのメンバーにも喜びとともに受け入れられ、周囲からの言葉や態度で嫌な思いをすることは一切なかったです。ただ、自分の中には不安がありました。3ヶ月も仕事から離れて復帰できるのだろうか、収入面で問題を抱えてしまわないだろうかといった不安です。育児休業給付金があること自体は知っていたものの、どういったタイミングでどの程度の金額を受け取れるのかなど、わからない部分も多々ありました。人事担当者との面談時に説明を受けたり、自分なりに調べたりすることで金銭面の不安は解消され、以降も申請の際など都度サポートを受けられました。ガイドブックにはどのタイミングで何をすべきかをカレンダー形式にまとめた資料があり、必要な作業をピックアップするのに非常に役立ちました。また、育休取得者が不利益を被らないよう、万一のための相談窓口も掲載されており、安心できました」

新しい世界に触れて成長する子が、頑張る意欲をくれる
ガイドブックの存在や個別面談に大いに助けられたという荒岡さん、育休中の3ヶ月間は新米パパとして奮闘したそうだ。
「出産後は妻の体調が思わしくなかったこともあり、しばらくは夜中のお世話も自分がメインでこなしていました。生まれてしばらくはよく泣き、夜中のミルクも頻繁で本当に大変でした。想像していた以上に負担が大きく、仕事との両立は難しかっただろうと改めて感じたものです。とはいえ、自分なりに頑張ったことで、非常に充実した時間を過ごせたのも確か。徐々に夜寝てくれる時間が長くなり、赤ちゃんなりに安心感や自分たち親との絆のようなものを感じてくれているような気がして、心からうれしく思えました。妻からも『いてくれて助かる』と感謝の言葉を受けとりました」
充実した3ヶ月を経て、いよいよ復帰が近づくと、荒岡さんは再び漠然とした不安を感じるようになったという。
「男性の育休としては比較的長い3ヶ月という期間ですが、過ぎてみればあっという間。全然足りないと思いました。同時に、仕事モードへちゃんと切り替えられるのか、子どもとの関わりが薄くなってしまうのではないかなど、育休前から抱いていたものに加えて育児面での不安も感じるようになったのです。とはいえ、いざ復帰してしまえば、職場のメンバーが温かく迎えてくれ、手をつけやすい業務から回してくれるなどスムーズに仕事モードに切り替えることができました。反面、仕事と両立しながらの子どもとの関わりについては現在もまだ模索中です。基本的にテレワークで通勤がない分、朝晩は時間をとって子どもとふれあうことができます。昼間は仕事に集中して遊べない分、夜は一緒にお風呂に入ったり遊んだりと、意識して接する時間を持っています。パパに対して人見知りする子もいる時期だと聞きますが、いまのところ問題ありません(笑)」
最後に、荒岡さんにとってパパ育業はどのようなものであったか聞いてみた。
「かけがえのない時間でした。子どもの成長は早く、その時にしか見られない姿やできないふれあいがあります。同時に育児は責任が伴う大変なもので、男親にもできることはたくさんあるということも感じました。子どもは常に新しい世界に触れ、頑張って生きています。その姿を目にすることで、自分自身も仕事やそれ以外のことも『頑張ろう』という意欲が湧いてくるようです。パパ育業を検討されている方がいれば、ぜひおすすめしたいですね」