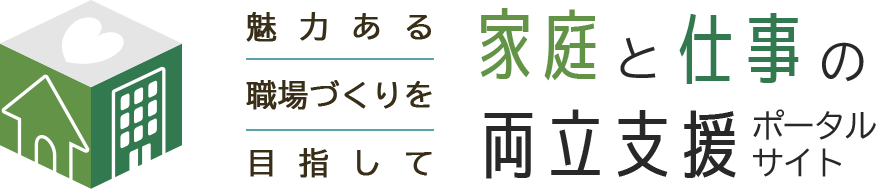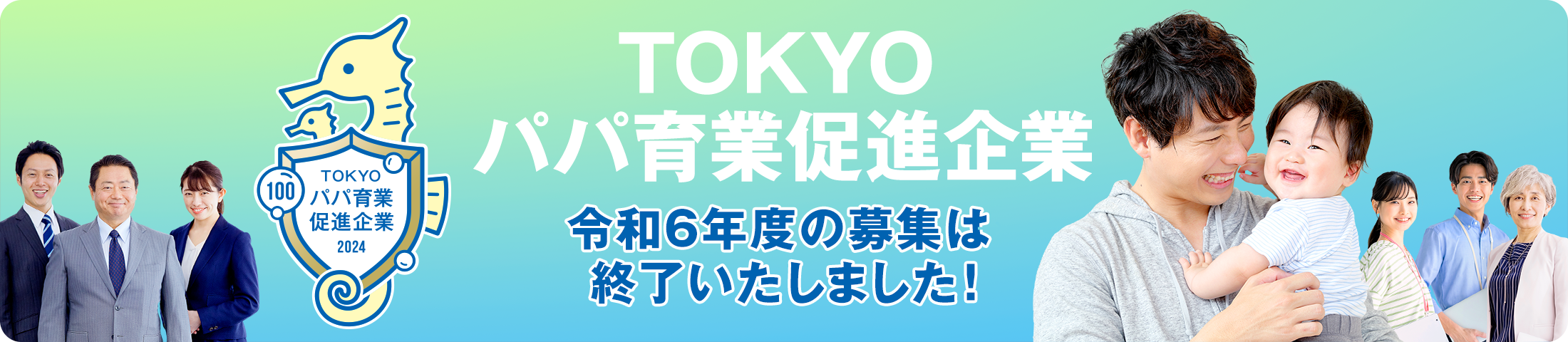取得者や周囲に孤立を感じさせないため
全社挙げてのバックアップ姿勢を示す

お話を伺った人
経営者・人事労務担当
日本物産株式会社
取締役専務執行役員
羽原 利尚 さん
日本物産株式会社
経営総務部長
野澤 朋広さん
従業員
日本物産株式会社
保険事業部 課長
伊藤 正之さん
セールスプロモーショングッズの企画、製造、販売などを手掛ける日本物産株式会社は、およそ8割が女性という社員構成。かねてより女性活躍の推進に取り組んでおり、2023年には「東京都女性活躍推進大賞(特別賞)」も受賞しました。近年、パパ育業においても推し進める取り組みをスピードアップ。女性活躍の領域で培ったノウハウを男性にも広げ、トップダウンでの制度設計に、ボトムアップによる取り組みも加えて、確かな成果を挙げています。ライフワークバランスの実現とエンゲージメントの向上に向けて、欠かせない施策としてパパ育業推進を位置付ける、同社の取り組みについて詳しく聞いてみました。
日本物産の3つのポイント
- 1.エンゲージメントや生産性の向上といった隠れたメリットに目を向け、社を挙げて育業を推進。
- 2.日頃から情報連携に取り組むとともに、個々の不安にも会社として取り組む姿勢を示す。
- 3.座談会開催や体験談の共有により、取得者の不安を払拭。
経営者・管理職インタビュー
INTERVIEW 01_取締役専務執行役員 羽原 利尚さん
男性育業推進が組織の生産性アップをあと押し
従業員満足度やエンゲージメント向上のミッションを受け、人事人財面での課題に対応するため、2024年4月に同社役員に着任した羽原専務。男性育業推進における同社の取り組みと実績への理解を通し、経営的な視点からは見落とされることも多い、その重要性を再確認したという。
「周囲への業務のしわ寄せなど、欠員によるデメリットに目が向きがちですが、育業には生産性の向上など、別方向でのメリットがあるのです。例えば、従来の担当者が当たり前に行っていた業務でも、引き継ぎにより別の人員が担うことでその必要性を改めて判定することができます。育業をきっかけに必要性の低い業務をスクラップできたという実例もあるのです」
また、育業が当たり前の組織では、部署内や部署間での情報共有が特に重要となる。事前に情報連携の体制を構築しておくことで、育業を容易にし、業務の効率アップにもつながるそうだ。
「当社では、ICT活用による情報連携に全社的に取り組んでいます。従来、個々が抱えていた情報をシステム上に載せることで、共有化を図り、万が一の突発的な事象にも対応可能な体制を作るのです。日常業務を遂行しながらバックアップ体制も構築しておけば、育業時の業務引き継ぎ負担も軽減されるでしょう」
例えば、チームでのメールシステムの共有や、見積書・提案書などを含む折衝記録や顧客情報のクラウド管理など、業務上の情報連携において、ICTはその威力を存分に発揮する。情報連携と相性の良いICTを活用することで、育業に限らず多様な働き方への対応が叶い、効率化も推進できたという。
「以前から取り組むべき課題とされてきたICT活用による情報連携が、育業をするあと押しとなっていることは間違いありません」

難局面が組織のバックアップ姿勢を示す好機にも
もちろん、育業をする社員の周辺では業務負担増が考えられ、それに対して他の社員が不満を持つことも考えられる。そうした個人の不満にこそ、チームとして、組織として対応していくべきだと羽原専務は強調する。
「育業をする社員も、それを支える周囲も、決して孤立してはなりません。そこで、昨年度より育業予定の社員がいる部署へ人事担当役員が訪問し、フォローする機会を持つ取り組みを実施しています。人員減という難局面を乗りきったからこそ見えてくる効率化などのメリットがあることや、それでも対応できないレベルの負担が生じた場合には、遠慮なく声を上げてほしいことなどを伝えています」
難局面を迎える部署を、組織としてバックアップする姿勢を示す良い機会となっており、育業する社員からもその周囲からも好意的に受け止められているそうだ。
「着任したばかりではありますが、男性育業への社内の意識の高さは実感しています。育業した社員が経験を共有することなどを通して、引き続き会社として育業を推進していくのだということも広く周知されており、いざ自分ごととなった際にも、育業をしやすい環境が整っているのではないでしょうか」
育業推進こそ、従業員個人の、あるいは組織としての成長を実現する好機と捉えているという羽原専務。ライフワークバランスをめざすうえで、また生産性や従業員のエンゲージメントを向上するためにも、欠かせない施策であると話す。
「デメリットばかり見て育業推進を避けるのは、経営上の損失であるともいえます。やってみたからこそわかるメリットが確かにあるので、まずはトライしてみていただきたいですね。私自身、育業してみたかったと思っています。生後間もない子どもたちとの絆が深まったことはもちろん、夫婦間での相互理解も進んだのではないかと考えています」

INTERVIEW 02_経営総務部長 野澤 朋広さん
トップダウンとボトムアップの双方から方法を模索
女性の比率が高いという社員構成から、女性活躍への取り組みは進めつつも、男性育業については特に取り上げてこなかったという同社。2018年ごろに働き方改革の一項目として男性育業の取得率向上を掲げたことを皮切りに、2021年に「育児目的休暇」を制定、2022年に「出産時特別公休」を3日から5日に拡充するなど、近年取り組みを急速に進めてきた。
「男性社員が少ないなかで、2022年には対象者2名が取得して100%を達成。うち1名は管理職であり、6ヶ月という比較的長期間にわたり取得するなど、育業しやすい環境にはなっていると思います」と話すのは、経営総務部の野澤部長だ。
「特に男性、女性と分けて考えるのではなく、女性活躍の推進で構築してきたノウハウをそのまま男性育業にも広げるというのが当社の方法論。トップダウンでの制度設計に加え、ボトムアップにより生まれる取り組みがあります」
2023年には「東京都女性活躍推進大賞」にて特別賞を受賞した同社には、「女性活躍推進ワーキンググループ」が構築されており、若手を含む社員から広くアイデアを募っているという。そこで出た意見や提言が、男性育業推進のあと押しとなっている側面もあるそうだ。
「女性活躍推進において見逃すことができないのが、『男性の家事・育児への参画』という課題です。そこで、男性育業推進により、社内全体の円滑なコミュニケーションも推し進めるという目標を掲げ、さまざまな取り組みの具体案を検討してきました。そうしたなかで、東京都による『パパ育業促進企業』の制度に辿り着き、申請・認定に至ったのです」
登録により社内外に取り組みを広報することで、企業価値を高めることはもちろん、社員一人ひとりへの意識づけや、多様な人財が働く社会に向けての好影響も狙ってのことだという。

上司同席の説明会で、職場理解を促進
同社では、男女問わず活用できる「産休・育休の手引き」や、育業中に利用できる福利厚生制度の情報をまとめたものを、全社員が常に閲覧できる社内掲示板に公開。育休者座談会を開催したり、体験談を社内報に掲載したりすることで、制度や実績を社内に周知している。
「取得希望者への育休取得説明会では、必ず上司にも同席を依頼し、職場の理解を得やすい環境づくりにも取り組んでいます。先日、私自身も部下の説明会に同席しましたが、知っているつもりでも知らないこともあり、勉強になる機会でした。制度として理解していても、いざ自分ごととなると疑問や不安が生じることも多く、それらを解消する機会としても活用いただいています。座談会や体験談を通して実際に育業を取得した人の声を共有することも、不安の解消に役立っているようです」
「さらに、休業前から休業中、復帰前と利用できるチャットツールも用意しています。対面での相談が難しい時期にも、『誰に聞いたら良いのだろう』『こういう時はどうしたら?』といった細かいことも気軽に相談できる環境です」
一方で、育業する社員やその周囲の業務負担をどう軽減するかといった課題もある。特に1ヶ月以内の短期間から数ヶ月と期間の差が大きい男性育業では、職場で業務フォローしきれるのかどうかの見極めが難しく、同僚の理解も含め、準備期も含めた支援の必要性を感じているという。
「育業する社員から『同僚に申し訳ない』といった声を聞くことが多かったことから、会社としてのバックアップ姿勢を示すべく、役員が該当部署を訪問して直接声を届ける機会も生まれました。さまざまな取り組みについての家庭内での対話が、パートナーの勤務先での制度づくりにつながったという話を聞きますし、逆に他社の制度なども参考にしていきたいと考えています。女性も男性も、仕事に育児にと活躍の場を広げ、いろんな意味での同士となれる社会をめざしていきたいですね」

従業員インタビュー
INTERVIEW 03_保険事業部 課長 伊藤 正之さん
ポストや評価への不安は上司のひと言で解消
入社16年目の2021年、課長職に就いた直後に第二子の妊娠が判明したという伊藤さん。長女出産時には精神的に不安定となった妻を支えることができなかったという反省から、次の機会があれば育業をしたいと考えていたにも関わらず、少し不安を覚えたという。
「社内で発信される情報に触れ、身近に育業経験者もいたことから、会社が育業を進めていることや、取りやすい環境であることは実感していました。しかし、いざとなると『重要なポストを外されるのでは』『評価はどうなる?』といった不安がよぎったのも事実です。周囲の反応も気になったので、まずは非公式に親しい同僚らに半年間育業をする意向を伝えてみました」
不安に反して好意的に受け止められ、続いて上司に相談。育業することと評価やポジションは切り離して考えるべきものと助言を受けて取得の意思がさらに揺るぎないものとなったそうだ。
「第一子の際の経緯から3ヶ月で少し落ち着いてきたことを思い出し、育業期間は6ヶ月に。妻とも相談し、育業の意思が固かったことから、上司に意思表示をするタイミングで、すでに引き継ぎ事項や休業中に起こりうることなどのリストを作成しており、共有の上でその後の進行なども相談しました」
2022年4月の第二子誕生と育業スタートに向けて、着々と準備を進めていた伊藤さん。だが、直前に家庭内で新型コロナウイルス感染が発生してしまったというのだ。
「せっかく立てたスケジュールは台なし。出社停止期間が続き、このまま挨拶もなしに育業に入るのは社会人としてどうかと思っていた矢先、育業前日にようやく出社できることに。約2週間を予定していた引き継ぎはたった1日で終えることになってしまいました」
産院も改めて探す必要があるかもしれないという追い詰められた状況で、周囲の温かいサポートは大きな助けになったと話す。

2人の「親」の存在で、家庭に余裕が生まれる
弟の誕生に、当初は意欲的だった長女が不安定になったことも受けて、育業の最初の2ヶ月ほどの赤ちゃんのお世話は、基本的にほぼ一人で担当した。昼夜問わず2〜3時間おきに空腹で泣き、ミルクを飲みすぎては泣き、下痢しては泣く新生児との生活は、想像以上にハードだったそうだ。
「まさに『こっちが泣きたいわ!』といった状況。また妻一人に任せていたらと想像すると恐ろしいです。長女を保育園に送った後に1時間半ほど仮眠の時間はもらっていたものの、毎日の睡眠時間は2〜3時間だったのではないでしょうか」
そんなハードな日々を送りながらも、2ヶ月ほど経つと徐々に楽になったと感じる瞬間が。赤ちゃんの世話にも慣れて、表情から大体の要望もくみ取れるようになってきたことで、楽しいと感じる余裕が出てきたそうだ。
「睡眠不足でイライラすることはあっても、娘も含めて強いストレスを感じることはほとんどなく、家族でのケンカもほぼなしで過ごせました。『親』という存在が家庭に2人いることで生まれる余裕が、安定につながったのだと思います」
三食の料理や片付けを含む家事や育児に慌ただしく過ごすうち、徐々に復帰の日が近づくと、不安も感じたそうだ。
「考えても仕方がないので『行けばどうにかなる』の精神で出社し、同僚の笑顔を見た瞬間に安心しました。会社のシステムが変わったこともあり、浦島太郎状態に戸惑う日々でしたが、周囲が明るく声をかけてくれたことで救われました」
復帰後も保育園の迎えなどを担当することもあり、できるだけ残業を発生させないための効率的な働き方を意識するようになったという伊藤さん。育業前は「6対4」で妻に任せることが多かった育児も、現在は「4対6」で担っているという。
「育児は長期戦。夫婦それぞれが得意なことを、分担してやっていかなければ到底回らないことも。育業をきっかけに、夫婦間で今後の体制などを話し合う機会が持てたのも大きな収穫でした。男女問わず、幸せな時間である育業が当たり前になってほしいと思います」