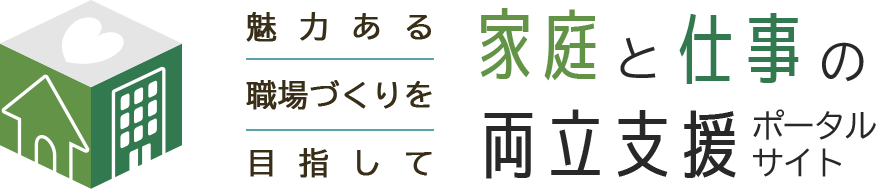歴史ある制度を時代に合わせて更新
価値観に合う働き方を選択可能に

お話を伺った人
日本アイ・ビー・エム株式会社
執行役員 人事担当
中村 拓さん
日本アイ・ビー・エム株式会社
人事 福利厚生 課長
椎名 裕美さん
日本アイ・ビー・エム株式会社
人事 福利厚生
青山 紘子さん
日本アイ・ビー・エム株式会社
コンサルティング事業本部 ハイブリッド・クラウド・サービス
内田 千尋さん
グローバル・テクノロジーカンパニーとして、AI、ハイブリッドクラウドなどのソリューションでビジネスの成長をサポートする日本アイ・ビー・エム株式会社。1911年創業と、アメリカ・ニューヨークに本拠を置くIBMは100年以上と古く、日本法人の立ち上げも1937年と歴史を持っています。そんな長い歴史を超えて大切にしている理念「ダイバーシティー&インクルージョンへのコミットメント」と、時代による変化の双方に合致するものとして、パパ育業も積極的に推進。多様な社員ニーズに応える制度設計と、各層の意欲的な取り組みにより、高い実績を叶えています。社員の声から生まれたという同社の育児支援制度誕生の背景や、現状にアップデートするための取り組みなど、詳しく聞いてみました。
日本IBMの3つのポイント
- 1.時代の変化と変わらぬ理念の双方に合致するパパ育業は、一人ひとりの価値観に合わせて判断を
- 2.子が1歳まで有給でとれる20日間の育児特別休暇新設など、歴史ある制度を時代に合わせてアップデート
- 3.経営層の働きかけに加え、社員の自発的なコミュニティ活動も制度活用を大きくあと押し
経営者・管理職インタビュー
INTERVIEW 01_執行役員 人事担当 中村 拓さん
「変わるもの」と「変わらないもの」の両方に合致するパパ育業
「1987年より性別を問わず対象となる育児休暇制度を導入し、実績も重ねてきましたが、現状で完全かと言われれば決してそんなことはありません。時代の流れとともに、社員のニーズはどんどん変わっていくものですから、今ある制度をしっかりと活用しながら、さらに良いものにしていくというのは、ある意味終わりのない道のりであると考えています」と中村さん。直近2年間で取得率がおよそ20%向上するなど、定着率や期間といった実績では大きな成果を見せている同社のパパ育業だが、まだまだ伸びしろが大きいと話す。
「1911年に創業して100年以上。国内法人としても90年近くの歴史を持つ弊社ですが、いわゆる昔ながらの会社という雰囲気はなく、制度や働き方の観点からも変化を続けています。一方で、考えよ『THINK』、社会とともに『Be a good corporate citizen』、『教育に飽和点はない』、『ダイバーシティー&インクルージョン』へのコミットメントといった理念・信条は長年継承。パパ育業は変化する時代のニーズに応えつつ、変わらぬ理念である『ダイバーシティー&インクルージョン』への決意も形にするものとして、積極的に推進しているのです」

あくまで一人ひとりの価値観を大切に、社員自身の判断を促す
「グローバル企業として、異なる文化的背景を持つ人材との協働が日常的にあり、多様な価値観を認め合わなければチームが回らない状況があります。性別問わず、メンバーが育児や介護などで家庭を優先すべきタイミングにあれば、どうバックアップすべきかといった議論も自然に発生します」中村さんは、パパ育業推進の背景として、同社の社内環境にも触れる。どんなレベルの社員でも意見を言え、相手はきちんと聞くという文化も根付いているという。
パパ育業推進を通して、自分らしく能力を発揮できる会社をめざすという同社の本気を社内外に発信することで、人を惹きつける企業になることができると中村さんは話す。新卒・キャリア採用のシーンではもちろん、社員のエンゲージメントの高まりも感じるという。2020年には社長が「男性育休100%企業宣言」もしたが、あくまで選ぶのは主役である社員自身。それぞれの価値観に照らして考え、自身ならではのキャリアを形作ることを求めるという。「『自分らしさ』を追求することは、古今を問わず変わらぬ価値観だと思っています。時代の変遷とともにその実現に手が届きやすくなっているのは素晴らしいこと。例えば、以前は希望を口に出すことが難しかったという人にもぜひ各制度を活用し、自分らしい多様な働き方を実現してほしいですね」

人事・労務部や当制度の担当者インタビュー
INTERVIEW 02_人事 福利厚生 課長 椎名 裕美さん/人事 福利厚生 担当者 青山 紘子さん
前世紀からの先進的な制度を、現代に合わせて更新
子の1歳の誕生日までに有給で取得できる20日の育児特別休暇や、法定より1週間長い7週間の産前休暇など、法律の基準を満たす制度に加えて独自の制度も提供している日本IBM。産前産後休暇は1974年、子の2歳まで取得できる育児休職も1987年からと、前世紀から当時としては先進的な制度を展開・運用してきた。
日本IBMでは「JWC(Japan Women’s Council)という諮問委員会が1998年に発足したのですが、これに先駆けて女性中心に声を挙げる文化があったようです。70年代、80年代の出産・育児に関わる制度の展開に加え、モバイルワーク、Eワーク、短時間勤務、看護休暇、介護休職なども、社会の変化や社員の声に呼応する形で制度化されました。現在は男性社員もJWCのメンバーとして活動しています。出産・育児に限らず、自分の働き方に合わせて選択できるよう、多様な制度が選択肢として用意されています」と椎名さん。
「『休職・休業』という表現では、長く休むというイメージになります。それでは取りづらいという社員の声も受け、2020年に制度化された育児特別休暇は、あえて『休暇』という形で、1日単位で取得できるものとなりました」と青山さん。長い休職は家庭の収入にダイレクトに関わるという声も受けて有給としており、育児特別休暇と通常の年次有給休暇、育児休職を組み合わせて取得するケースも多いそうだ。
「例えば職場の状況によっては1ヶ月丸々不在となってしまうことが難しいこともあり、育児特別休暇は分割での取得も可能としています。週のうち数日休んで残りの日に業務をこなすといった使い方もでき、それなら取得ハードルが下がるとの声も届いています」

上層部の空気感醸成は必須。多様な手法で各層にアプローチ
社員の声をきめ細かく拾いあげ、ニーズに応える多様な制度設計をめざしているというが、選択肢が多くなるほど複雑化が避けられず、周知が難しくなることは課題だという。制度を正しく理解し、適切に利用してもらうために、月に一度人事で主催するマネージャー向けのセッションなどの機会を利用して、積極的に制度を紹介するなどしている。制度を活用しやすい空気感を社内に醸成するためには、上層部の働きかけも欠かせないとし、社長や役員が積極的に育児を話題にあげたり、育児を目的とする休暇への理解を示したりすることが、有効に働いているそうだ。「どんなに良い制度があっても、活用されなければ意味がありません。定期的な1on1面談の際などに自身のプライベートを含めた経験をシェアする上司も少なくないそうで、そうしたコミュニケーションの文化が根付いていることもあと押しとなっているようです」
「社内のコミュニティ活動も大きな助けになっています。コミュニケーションツールを用いたワーキングペアレンツコミュニティがあり、育児中の社員はもちろん、これから育児に臨む者、まだ予定もない者も含めて、およそ800人の社員が参加。活発に情報交換しています。その中に福利厚生活用というチャンネルもあり、『こんな制度が使えるよ』といった実体験に基づく声を広く届けてくれているのです。こうした社員がいることがまさに弊社の魅力だと感じます」と椎名さん。出生時に限らず、乳幼児期、学童期、受験期など、長く続く育児の各段階をテーマとしたトピックが隙間なく用意されており、個人的にも大いに活用していると話す。1~2か月に一度、テーマを設定してのランチ会もオンラインと現地のハイブリッドで開催されており、自分に合う内容のものに自由に参加可能。仕事で全く関わりのない人ともつながりを持て、少し距離がある関係だからこそ本音で語れる側面もあるようだ。
取得率の向上により、身近に経験談を耳にする機会もさらに増えることが予想されるとし、一層の制度展開も模索しているという二人。
「休暇休職に限らず、自身のキャリアは自分で考えて決定すべきというのが弊社のカルチャー。社員の声に耳を傾ける姿勢を大切に、継続的なアップデートに努めたいですね」と笑顔で締めくくった。

従業員インタビュー
INTERVIEW 03_従業員 内田 千尋さん
育業から復帰後、急遽もう一度2回目の育業へ
ITアーキテクトとして、BtoB顧客のシステム設計・開発を担うチームでプロジェクトを担当している内田さん。2023年6月第一子である長女の誕生を機に、育業に入ったという。
「生まれた直後からの3ヶ月間に加え、生後半年を迎える頃からの3ヶ月間と、結果として2度の育業を経験しました。当初は2度目の予定はなかったのですが、1度目の育業から復帰した際に、育児と仕事のバランスを取るのが難しく、どうしても負担が偏った妻が体調を崩しかけたという背景があったのです。復帰後1ヶ月半というところでしたが、急遽業務を再調整させてもらいました」
「復帰直後の再調整となったため、言い出す際には不安でした。復帰後は多忙なプロジェクトに入っており、スケジュールや自身の業務に追われる中で、果たして再度の育業が叶うのかという不安です。実際に相談する際には、上司やプロジェクトリーダーにも家庭を優先したいという希望に賛同してもらえました。現場で一緒に働いているメンバーにも状況を話すと『それは再度の育業が必要だ』と理解してもらえて、ありがたく感じたものです」
周囲には、日頃から保育園の送迎を担っていたり、熱を出した子のために仕事を調整したりといった育児と並行する働き方をしている社員も多かったことから、「今は仕事より家庭を」と背中を押してもらえたそうだ。制度の活用などについては、社内コミュニティの体験談も参考にしたという。

育業は子どもとの持続可能な働き方の土台づくり期間
「1度目は子も生後間もないこともあり100%育児といった感じで、昼夜問わず妻と交代でミルクをあげたりオムツを変えたり。時間のほとんどすべてを育児に使う生活でした。生後3ヶ月くらいまでがやはり一番大変な時期だと思うので、そこを二人で分担しながら協力できたのは、とても良かったと思っています」それぞれが育児に慣れて、家事と並行しながらもひと通りこなせるようになり、どちらかが外出しても問題なく過ごせるようになったのも大きな成果だったそうだ。
「2度目の育業で強く意識したのは、またいずれ復帰することになるという点。持続可能性というか、仕事復帰をしても回していけるようにするにはどうすべきかを念頭に、家具の配置や家事の効率化など、妻とも話しながら少しずつ改善していく時間に。互いに余裕が出てきたので、英語学習などキャリアアップのための勉強の時間も取れました」
目の前のことに精一杯だった1度目育業からの復帰を経て、その反省も活かしながら、2度目ではさらに実りある時間を過ごせたそうだ。
「自分の場合、復帰にあたって仕事での不安や問題はありませんでした。2度目の育業から復帰した際には、上司からマネージャー職に就くことを提案され、新しいチャレンジとして取り組んでいます。子どもを持つ前に比べ、時間のコントロールもより意識するようになり、仕事へのモチベーションも向上。家庭と両立しながらも、自分なりにうまく回せている手応えを感じています」と内田さん。仕事にかけられる時間は限られるようになったものの、充実度は高まったと笑顔を見せる。
「スムーズに育業に入るために大切なことは、早めの調整と収入減への対策。出産前にもつわりや妊婦健診への付き添いなどへの対応が必要ですし、お金の面では給付金もありますが、入金のタイミングまでにベビーカーなどの大きな出費が重なることもあります。また、予定通りに行かず、延長や2回目も可能性としてあることを認識しておくこともおすすめします。可能であれば、復帰前の段階で復帰後の生活を想定してリハーサルしてみるのも良いのではないでしょうか」
これから二人目の誕生が予定されており、年子育児にチャレンジすることになる内田さん。次は4ヶ月半の育業に向けて、調整を進めているところだ。
「この時期の子と全力で向き合える時間は貴重なもの。家族みんなでより良い未来へ向けてがんばっていこうと、とても前向きな気持ちになれるパパ育業、検討中の方がいればぜひおすすめしたいです」