社員それぞれの背景に家族がある
その意識からパパ育業推進をスタート

お話を伺った人
株式会社ジャノメ
人事部 部長
宮本 幹さん
株式会社ジャノメ
産業機器研究開発部開発第一グループ グループリーダー
釜井 善弘さん
株式会社ジャノメ
家庭用機器研究開発部開発第一グループ
石黒 博史さん
日本初の国産ミシンメーカーとして、家庭用ミシンから産業機器までを幅広く製造、販売する株式会社ジャノメ。2021年には創業100周年を迎え、業界のリーディングカンパニーとして世界中の社会、文化の向上にも貢献しています。社員一人ひとりの多様性を認め、働きがいのある組織づくりにも取り組んでおり、近年「出生時育児休業(産後パパ育休)」を拡充するなど、パパ育業推進へのアクションも多彩。そんな同社で、パパ育業に関わる制度の設計・運用を統括する人事部長と、パパ育業を経験したお二人にお集まりいただき、座談会形式でお話を伺いました。
ジャノメの3つのポイント
- 1.まずは社員それぞれの背景にある家族の存在を意識することからスタート
- 2.有給の「産後パパ育休」を14日に拡充し、育業中の収入不安にも対応
- 3.周囲へのフォローとマネジメント層の理解が今後の課題。「お互いさま」を形にする仕組みづくりに取り組む
インタビュー
まずは一人ひとりの背景にある家族の存在を意識することからスタート
御社の「パパ育業」に関わる取り組みを教えてください。
当時は自分ごととして捉えてはいませんでしたが、経験談を聞いて「社内にそんな人がいるんだな」と、心の片隅になんとなく認識したような記憶はあります。
当社は2008年に厚生労働大臣認定の子育てサポート企業「くるみん」を取得するなど、社内外へワーク・ライフ・バランスに関する取り組みの周知に努めてきました。2022年10月には「出生時育児休業(産後パパ育休)」として14日まで有給扱いとするよう制度を拡充。東京都のパパ育業促進企業登録にあたっては、弊社のクリアできる条件が「ブロンズ」であることに実は少し議論も。ただ、「ブロンズ」だからこそ伸びしろがある。「ゴールド」をめざしてがんばるぞという姿勢を示すこともできるのではないかと登録に至りました。
具体的にどのような制度があるかは知らずとも、なんとなく社内にそういった取り組みがあるんだろうなとは思っていました。名刺にもくるみんマークなど様々なマークが掲載されていますし。
有給の「産後パパ育休」が14日間に拡充され、収入面の不安も解消
育業に際しては、どのように決められたのですか?
ちょうど子どもができたタイミングで上長と面談する機会があり、報告すると、「育業するでしょ?」と上長の方から提案されました。上長も以前に育業に入った経験があったそうで、社内の制度も良くなっているはずだから、詳しくは人事に相談してみるようにとアドバイスされました。
私の場合、チームリーダーになって数ヶ月というバタバタした時期でもあったことから、できるだけ早めに意思表示したいと3ヶ月くらい前から上長に相談しました。ありがたいことに温かく受け入れられ、その後グループ内での業務調整に入りました。
上長が育業経験者だったというのは、何よりのあと押しだったことでしょう。マネジメントする立場の社員が育業を前向きに捉え、当事者の希望を温かく受け入れてくれているのはうれしいことです。

育業に向けて不安はありませんでしたか?
新しいプロジェクトに配属されて間もなく、スケジュール的にタイトすぎないタイミングだったのが幸いしました。私の場合、有給の産後パパ育休14日に加え、土日などと合わせて約1ヶ月の育業期間を確保させていただいたので、収入面での不安もなし。どの制度をどのように利用するのがベストかなど、人事担当者に相談し、調整もお願いできたので助かりました。
不在中に業務上支障がないかという点と、収入面の2つの不安がありました。業務については時間をかけて、早めに業務の調整に取り組んだことで、グループメンバーともしっかり話し合って対応できました。収入については調べきれていなかったので、わからないことによる漠然とした不安という感じです。制度化されたばかりの産後パパ育休が社内で告知されており、これが適用されるのではないかと人事に相談しました。詳しく説明を受け、プラスで有給の積立保存休暇※2を20日加えれば、手取りを減らすことなくこのくらいの期間を確保できるという提案も。おかげで収入面でも不安もなく、育業に入ることができました。
パパ育業の経験が家族の絆を深め、業務の効率化意識も向上
育業中はどのように過ごされましたか?
最初は3時間おきのミルクが必要で、交代で睡眠をとりながら赤ちゃんのお世話をする生活。まとまった睡眠が取れなかったり、思うようにミルクを飲んでくれなかったりと大変なこともありましたが、とにかくかわいくて! 新生児期ならではのかわいらしい姿を夫婦二人できちんと味わえたのは、とても価値あることだと思っています。
双子だったこともあり、正直きつかったイメージしかありません(笑)。二人でやってもこれだけ大変なのに、一人でやるのは無理だと。改めて育業を選択してよかったと思いました。育業中、実父と話す機会があったのですが、育児に奮闘する私の姿を見て「自分の時は難しかったが、こうしてしっかりと赤ちゃんと向き合えるのは良い時代だ」と言われました。当時の父は仕事優先で、私たち子どもの小さい頃の記憶がないそうで、その点、喜びも、かわいらしさも、そして辛さもしっかりと刻むことができた私は幸福です。
私の時もこうした制度がなかったため、育児は完全に妻に任せきりになってしまった。土日はあったものの、関わりの深さが全然違いますね。心からうらやましいと思いますし、こうした話を聞くと制度の設計や運用への意欲を改めて掻き立てられます。子どもが小さくかわいらしい時期からしっかりと関わることで、子どもたちのパパへの感情も違ってくるのではないでしょうか。わが子は成長してすっかり大人になってしまいましたが、すっかりママっ子です(笑)。
復帰についてはいかがでしたか?
タイミングが良かったのもあり、スムーズに戻れる環境でした。新生児期は過ぎたとはいえまだまだ子に手がかかる時期だったので、復帰当初は残業をなるべく控え、できるだけ仕事を定時内で終わらせるよう努めていました。今もそうした意識は持っていますね。
想像していた大変さはありましたが、グループのメンバーがしっかり仕事を分担してくれていたこともあり、想像を超えるような大きな負担はありませんでした。育業を経て、無意識のうちにできるだけ早く帰ろうという意識はありますね。効率化という意味での意識の変化です。一刻も早く帰ってパパの役割を果たさなきゃと。

気負い過ぎず、怖がらず、まわりを信じてパパ育業に挑戦を
パパ育業促進において、課題と感じていらっしゃることはありますか?
一つには当事者を支える周囲へのフォロー、そしてマネジメントする側の理解が課題だと考えています。どうしても世代が上になるので、古い考えが残っていたりする。そうしたマネジメント世代の意識をリフレッシュするアプローチは必要です。周囲へのフォローについては、より気持ち良く育業でき、より気持ち良く育業に送り出せるような仕組みづくりができればと人事部内でもよく議論しているのですが、これという策が見つからないのが現状です。お金で解決する方法もあるでしょうが、別の生き方をする人にも「お互いさま」の気持ちで受け入れられるような方法があればと考えています。
今後、パパ育業を検討している人に向けてメッセージをお願いします。
気負い過ぎず、怖がらず、まわりを信じて育業にトライしてみてほしいと思います。経験者の話で印象深かったのが、「仕事への影響という面では、ちょっと長いお正月休みや長期出張のようなもの」という表現。社員の代わりはいても、父親の代わりはいませんし、得られるものの大きさに比べれば、負の影響は微々たるものだと思うのです。
おそらく、最初のひと言に一番勇気が必要です。育業を希望する意思表示をして良いものか躊躇する場面もあるでしょう。そんな時、まずは相談という形で切り出してみるのも良いのではないかと思います。育業する、しないを含め、どういう方法があるのか相談することで見えてくることも。「育業します」との宣言よりは、「育業してみたいのですが」との相談の方が口にしやすいですよね。
自分は本当に育業して本当に良かったと思っています。子どもが生まれて最初の大切な時期をしっかりと関われたからこそ、深い絆を築けて、いまもこうして愛着を持って子どもに接することができていると感じるのです。パパ育業を検討しているなら、ぜひおすすめしたいですし、身近にいれば、全力でバックアップもしていきたいと思っています。

- ※1 ジャノメファミリーデー
- 従業員の家族を対象とした会社見学会。職場内における「仕事と家庭の両立」に関する理解を深め、働きやすい職場づくりを目的とするもの。
- ※2 積立保存休暇
- ジャノメでは積立日数最高45日のうち、出生時育児休業期間および育児休業期間を通して最高20日間充当することができる。

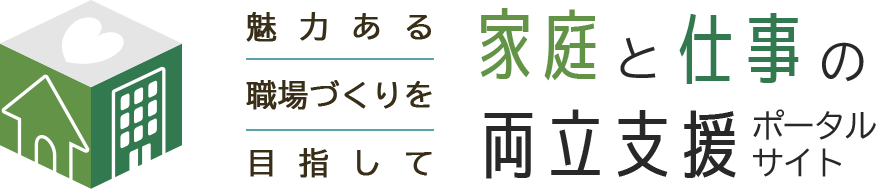




採用面でも、せっかく採用した人材の定着率向上のためにも社員満足度を上げたいという点でも、働き方の改善が求められていました。まずはそれぞれの社員の背景にある家族の存在を互いに意識するきっかけとして、2016年に「ジャノメファミリーデー」※1を開催。当時は開発部門に在籍しており、社員の一人として参加しましたが、家族の大切さを改めて認識する機会であったと思います。2018年には育児に関わる休業制度を紹介する説明会を開き、実際に育業を経験した人から体験談を聞く機会を設けました。