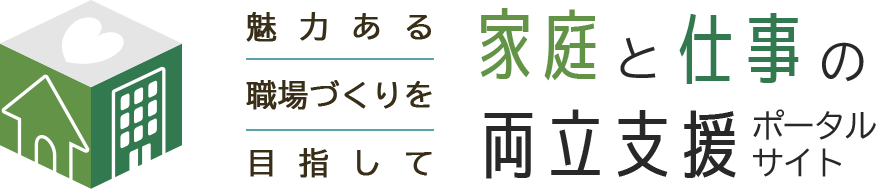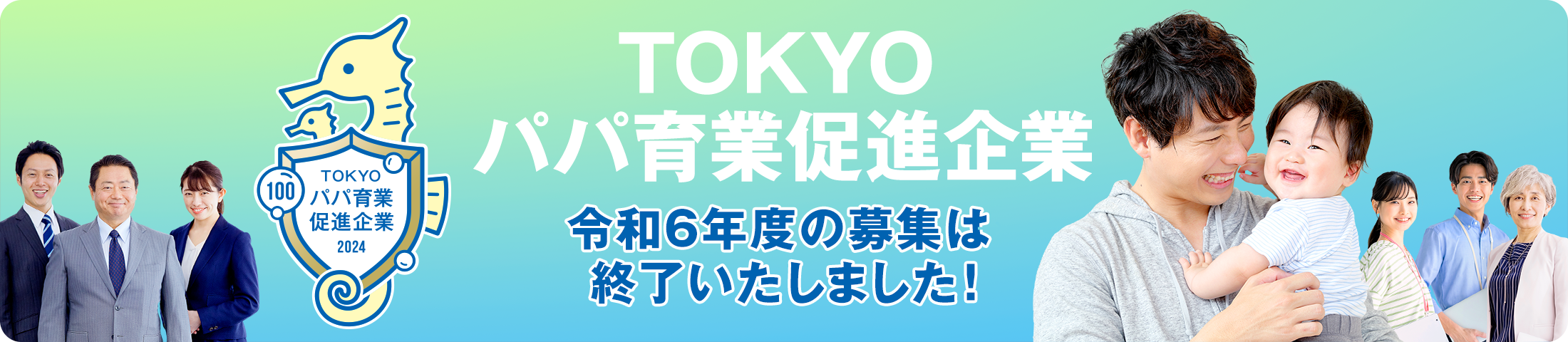パパ育業を当たり前に。
その土壌づくりが、従業員のパフォーマンスを高める。

お話を伺った人
経営者・人事労務担当
東急株式会社
常務執行役員 人材戦略室長
芦沢 俊丈さん
東急株式会社
人材戦略室 労務企画グループ 主査
牧野 彩さん
従業員
東急株式会社
ビル運用事業部 営業統括グループ 主査
吉川 重和さん
東急グループの中核企業である東急株式会社は、交通、不動産、生活サービス、ホテル・リゾートなど、お客さまの生活に密着した幅広い事業を展開しています。同社は、2014年にダイバーシティ推進を担う専属チームを設置し、15年には「男性育業取得率100%」の目標を策定。「育業の一部有給化」「管理職向け研修内での啓発」「取得事例の社内公示」などの取り組みを通じ、育業を当たり前に取得できる土壌づくりを推進しています。そんな東急株式会社の常務執行役員(人材戦略室長)、労務担当者、そして育業取得者の3名に話を伺いました。
東急の3つのポイント
- 1.男性育業取得率100%の目標策定。2022年度時点で90.6%の実績。
- 2.育業の一部有給化(最大53日)、管理職への啓発活動、取得事例の社内公示など、制度・風土の両面で育業取得を後押しする取り組みを実施。
- 3.全社として、育業を取得することが“当たり前”の雰囲気を醸成し、家庭にも事業にも好影響を生み出す。
経営者・管理職インタビュー
INTERVIEW 01_常務執行役員 芦沢 俊丈さん
直近8年間で、男性育業取得率が2.1%から90.6%に向上。
経営トップのコミットメントのもと、10年ほど前からダイバーシティを積極的に推進している東急は、取り組みの一環として2015年より「男性育業取得率100%」の目標を掲げている。目標策定後、14年度に2.1%だった取得率は劇的に改善し、22年度の実績は90.6%に。その背景や推進にかける想いを、常務執行役員・人材戦略室長の芦沢さんに聞いた。
「創立100周年を迎えた東急は、鉄道事業がルーツである特性上、宿泊勤務なども多く、長らく男性中心の会社運営が行われてきました。しかし、近年では女性運転士の増加をはじめ、さまざまな分野で多様な人材が活躍する会社へと変化を続けています。さらなるダイバーシティの推進に必要なのが、男女ともに活躍できる環境整備や、従業員同士が理解・尊重しあえる風土形成。その実現に向けた取り組みの一つが、男性の育業取得率向上です」。
目標を策定した当初は、「100%」という極端な数値目標に懐疑的な声もあったという。
「会社の歴史的な背景もあり、当時はダイバーシティという観点で世の中から遅れをとっている認識がありました。その遅れを取り戻すためには、会社として本気で取り組まなければならない。そして従業員に本気度を伝えるためにも、「100%」に意味があったのだと思います。東急は変わろうとしている、変わらなくてはならない、そうしたメッセージにもなったのではないでしょうか」。

パパ育業は、「家庭も事業も育む」。
「育業の取得は、子育ての喜びや大変さをパートナーと分かち合える、人生の中でも貴重な時間を生み出します。その経験は、取得者とご家族のQOL (クオリティ・オブ・ライフ)を必ずや向上させるものだと思います」。そうした従業員個人へのプラス作用とともに、事業への好影響も多分にあると芦沢さんは言います。
「一つは、取得者に関わる周りの従業員への影響です。男性も育業を取得するのが当たり前の雰囲気が醸成されることで、通常は、離職や異動時にしか行われない業務の棚卸し・引き継ぎ・共有が必要となります。その結果、日常的にお互いをフォローし合う姿勢や、効率化への意識が高まり、従業員一人ひとりのパフォーマンスが向上したと感じています」。
「また、“一人のパパ”として、子育てに向き合うことは、生活者としての視野を広げるきっかけにもなります。例えば、子どもを連れての移動や、育児に必要な商品の購入などは、当事者にならないと気づけないポイントが沢山あるはずですよね。世の中にはいろんな人がいて、多様なニーズが存在する。それらを肌で感じることは、お客さまに寄り添った新しいサービスや事業の創出にもつながるのではないでしょうか。これは当社の事業に限らず、あらゆる企業にとっても当てはまる事実だと思います」。
「男性育業には、家庭も、事業も育む力がある」と語る芦沢さんの言葉には、強い実感が込められていた。
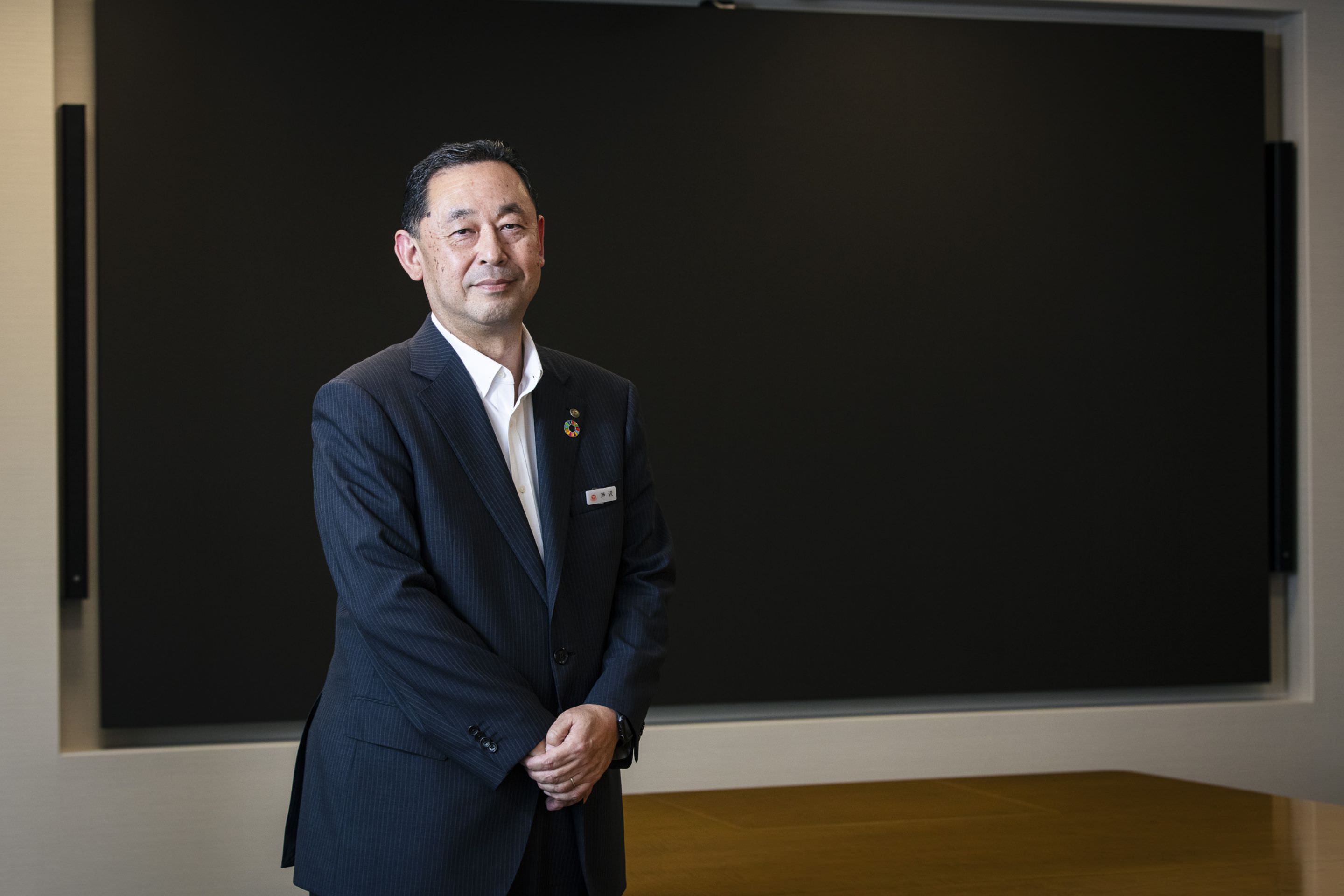
INTERVIEW 02_人事労務担当 牧野 彩さん
制度と風土、両面からのアプローチが重要。
ダイバーシティ専任チームの一員として、男性育業の取得推進に関するさまざまな施策の企画・運営を行っている牧野さん。具体的な取り組みや、男性も当たり前に育業を取得できる雰囲気づくりのために意識しているポイントを伺った。
「例えば制度面では、育業の一部有給化を行っています。育業時の給付金の受取額は約7割。一般的に手取りが減ってしまうことが、取得のネックのひとつだと言われていますが、当社では「保存年次休暇」などを利用して、最大53日間、有給休暇として取得できるようにしています」。
もちろん、各種制度があるだけでは、根本的な解決にはならないと牧野さんは続ける。
「制度があったとしても、“本当に使えるの? キャリアに響かない?”というのが、従業員の正直な反応だと思います。だからこそ、育業推進の初期段階では、制度を理解してもらうことや、管理職層へのアプローチに注力しました。管理職向けの研修などで、事あるごとに案内・啓発を行ったり、未取得者をリストアップし、上長からの声がけを促したりしていきましたね。草の根運動と言いますか、まずは地道に発信を続けることが大切だと思います。そのほかにも、取得事例を社内報などに掲載したり、育業取得者とその上長へのインタビュー内容を当社ウェブサイトに公開したりすることにより、“育業をとることが、当たり前”という雰囲気を醸成するための施策に取り組んできました」。

誰もが働き続けたい。そんな会社の実現に向けて。
「男性育業取得率100%」の目標を掲げてから、10年足らず。数字上の実績だけでなく、社内の認識・雰囲気も着実に変わってきているという。
「“あの人が取ったから、おれも取ろうかな”という雰囲気はできつつありますね。子どもが生まれる際に育業を取得することは、本人にとっても、周りの従業員にとっても自然な流れになっていると思います」。
さらなるダイバーシティの推進に向けて、今後の展望についても語ってもらった。
「まずは、100%を達成すること。もちろん数字がすべてではありませんが、分かりやすい指針としてこだわりたいです。ここ最近の未取得者は、中途入社の従業員が比較的多い傾向にあります。おそらく前職には育業を取る文化があまりなかったことで、当社内において“育業を取りたい”と申し出るのを躊躇してしまうケースもあるのではないでしょうか。そうした方々へのアプローチは、今後も注力していきたいと思っています」。
男性育業の取得を推進することによって、牧野さん自身にも新しい視点が芽生えた。
「本当の意味での多様性とは、育業を取得する人だけでなく、育業中に業務をフォローする人の気持ちも大切だと考えるようになりました。さらに現在は、育業に限らず、介護などに従事する人を含め、すべての従業員がいきいきと働ける環境・風土づくりに取り組んでいきたいと思っています。男性の育業取得推進で得られた経験やナレッジを、より広い意味でのダイバーシティ推進に向けて活用していきたいですね」。
働きやすい会社づくりは、従業員の会社に対するエンゲージメントを向上させ、業務パフォーマンスを高めることや、新たな人材の採用においても有効に作用している実感があるという牧野さん。
「男性の育業取得をはじめ、ダイバーシティを推進し、誰もが働き続けたい会社を実現すること。それは、持続的な事業経営にもつながっていくはずです」と、締めくくった。

従業員インタビュー
INTERVIEW 03_従業員 吉川 重和さん
育業取得で、仕事への向き合い方も変わった。
ビル運用事業部所属の吉川さんは、東急が全国に展開するサテライトオフィスの運営・管理をする業務に従事。2018年、2020年、2022年と、3度にわたり育業を取得した経験を持つ。第一子の育業期間は、9.5ヶ月。存分に制度を活用しているように見える吉川さんに、取得に至った経緯を聞いた。
「第一子の出産がわかったときに、まずは上司に相談をしました。当時は育業のイメージがあまり沸かず、キャリアへ影響するのではという不安もあったのですが、上司からの『子どもの成長はあっという間だから絶対に取得した方がいい。昇進や評価にマイナスに働かないことも、人事にしっかり確認するよ』という言葉に背中を押してもらえました」。
育業の取得によって、自身の考え方にどんな変化があったのか。当時を振り返りながら語ってくれた。
「家族と沢山の時間を過ごしたことで、子どもがいる生活に早い段階で慣れることができたのは大きいですね。仕事をしながらだと、どうしてもパートナーに任せることが増え、時間がかかるものだと思いますから。育業期間中に、育児にかかる時間や大変さを十分理解できたことで、復帰後の心の余裕にもつながりました。また、家庭と両立するためには、どうすればいいのか?という感覚が染みつくので、普段の業務の中でも、自然と工夫や効率化を図れるようになったと感じています」。

パパ育業は、生活の土台づくり。
育業期間は日々の子育てだけでなく、マイホームの購入検討や、子どもたちの保育園を探す時間にも充てられたという吉川さん。
「ライフプランの設計や、生活の土台づくりの時間をしっかりと持てたのも、育業取得によって得られた価値だと思います。やるべきことが明確になり、取得前よりも仕事に集中できている感覚がありますね」。
会社が育業取得を後押ししてくれたことで、仕事で還元したい、周りの仲間たちをサポートしたいという気持ちも強く芽生えた。
「相談に乗ってくれた上司や、業務を引き継ぎ・フォローしてくれた方への感謝の想いを強く持ちました。恩返しではないですけど、しっかりと仕事の成果でお返ししていきたいです。そして、年次やキャリア的にも今後は後輩や部下が、育業を取得する機会が増えていくと思います。そのときには、私が上司に後押ししてもらったように全力で応援したいですね。実体験による具体的なアドバイスもできればと」。
最後に、吉川さんに「パパ育業とは?」と質問をしてみた。
「私の今の生活は、家族との絆という側面でも、人生設計という側面でも、仕事と家庭の両立という側面でも…、育業が取得できなければ、成立していなかったものが沢山あると思います。“取れたら助かる”ではなく、“取れないと困る”。そんな必要不可欠なものだと言えますね。そしてそれは、私だけでなく会社全体、世の中全体にもあてはまるのではないでしょうか。人材確保の競争や、一人ひとりの生産性向上が求められる社会において、育業の推進をはじめ、多様な人材が活躍できる組織をつくることは、すべての企業にとって、必要不可欠な取り組みだと思います」。