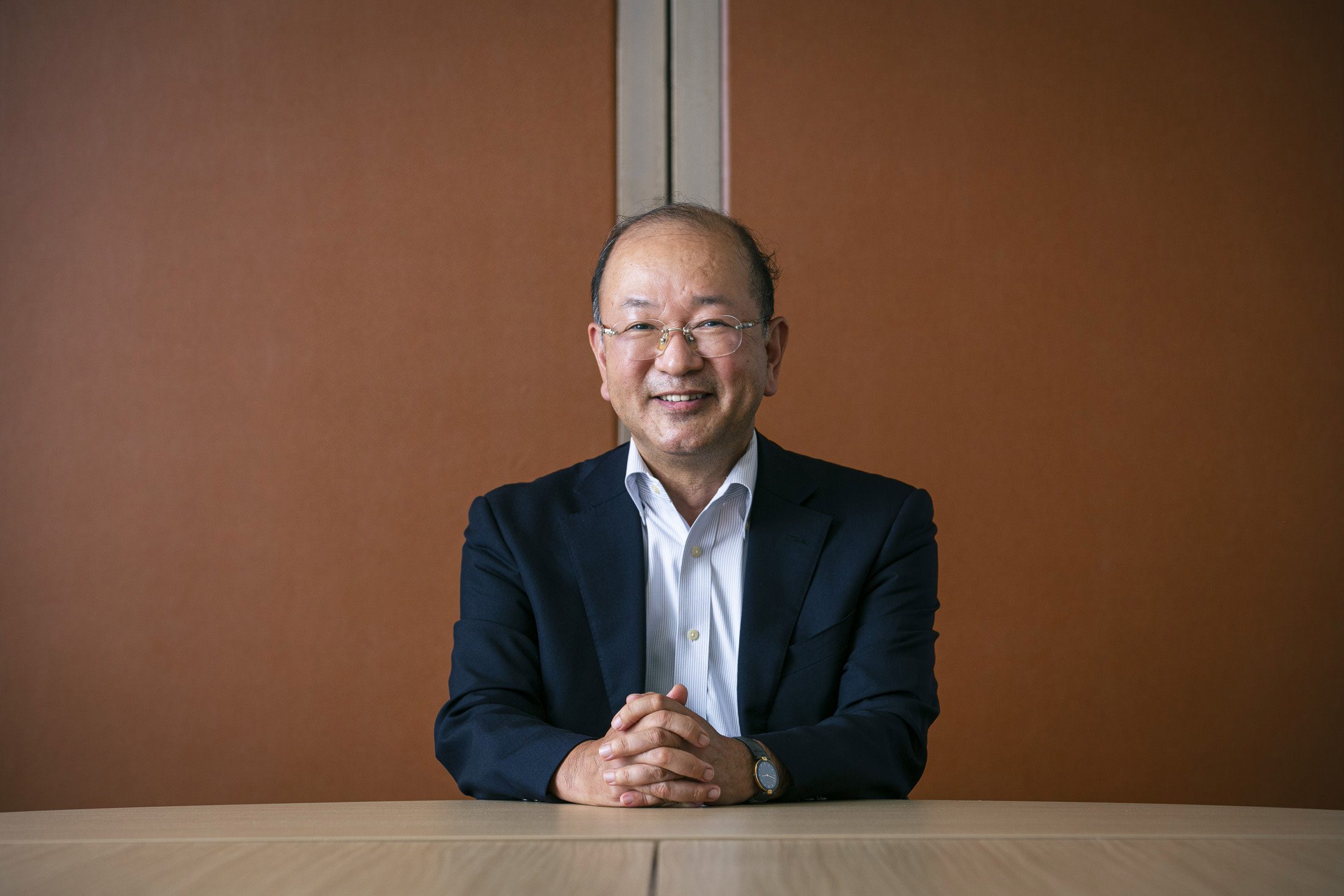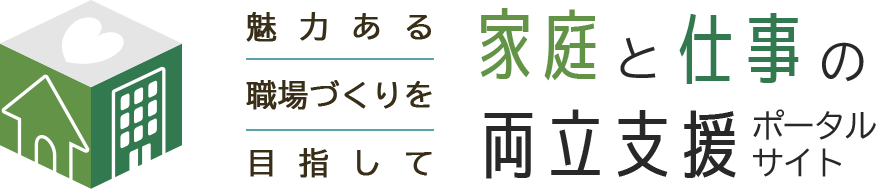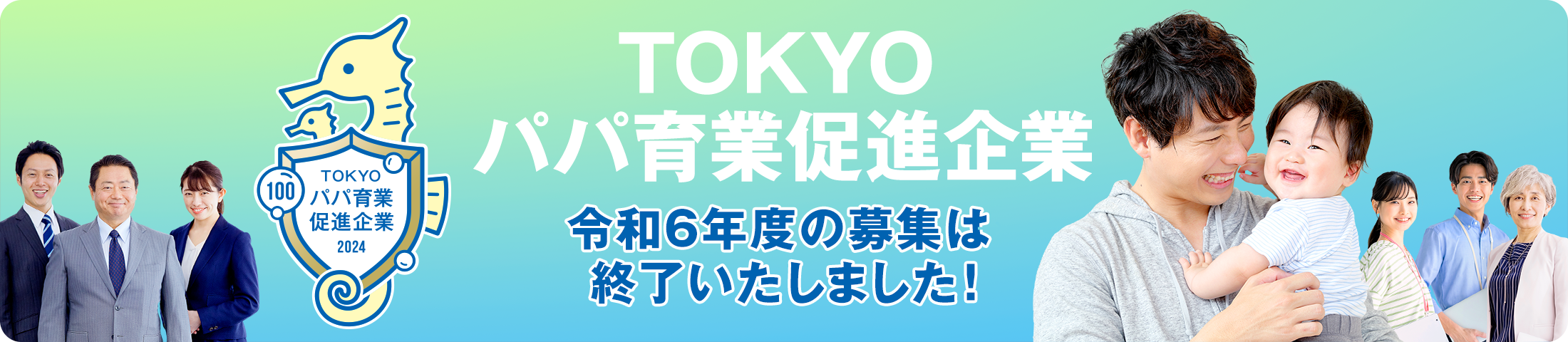選択肢としての男性育業が、「個の自律」を促進する。
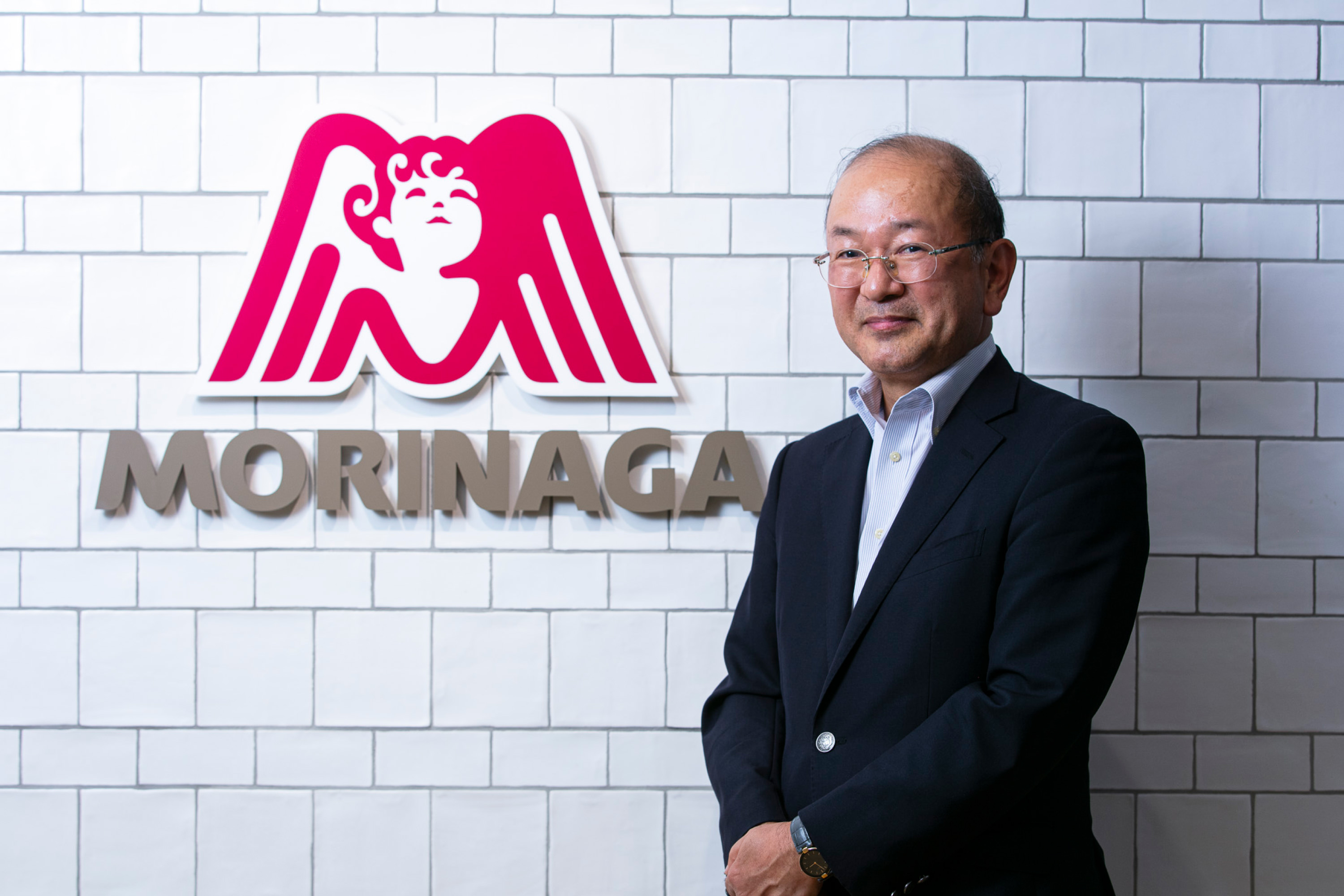
お話を伺った人
経営・人事責任者
森永製菓株式会社
上席執行役員 人事部長
高橋 正明さん
1899年の創業以来、日本の人々に栄養価のあるおいしい菓子を届けたいという大きな夢を抱き、様々なチャレンジを積み重ねてきた森永製菓。「一人ひとりの個を活かす」という考えのもと、多様な人材が活躍できる組織づくりに力を注いでおり、6期連続で国から『子育てサポート企業』として認定され、2017年9月からは『プラチナくるみん』の認定基準を継続的に達成しています。そんな同社の上席執行役員で人事部長の高橋さんに、男性育業に対する考え方や取り組みについてお話を伺いました。
森永製菓の3つのポイント
- 1.「育児休業の一部有給化」や、「社内報」による制度等の紹介により、制度・風土の両面で育業取得を推進する。
- 2.人から人への伝播が、男性育業を取得しやすい文化を醸成する。
- 3.男性育業を、個人のキャリア自律、経営戦略の実現にもつなげていく。
経営・人事責任者インタビュー
INTERVIEW_上席執行役員 人事部長 高橋 正明さん
育業取得率だけでなく、その背景にも目を向ける。
「世代を超えて愛されるすこやかな食を創造し続け、世界の人々の笑顔を未来につなぎます」をパーパス(使命)に掲げる、森永製菓。その実現に向けた原動力は「人」、そしてその力を最大化するのはダイバーシティ&インクルージョンの実践と捉え、経営戦略の中心として位置づけている。そんな同社の男性育業取得率は、2022年度に66%と着実に上昇しているが、数字だけでは測れないものもあると、人事制度の責任者である高橋さんは語る。
「仮に育業を『必ず取得しなければならない』『●日以上は取得しなければならない』といったルールを導入すれば、取得率はさらに向上し、平均取得日数も増えるはずです。しかしながら重要なのは、従業員に選択肢があることだと考えています。大前提として、安心して気兼ねなく取得できる土壌がある。その上で、仕事観やライフスタイルに合わせて自分で判断できる。これこそが、本当の意味での多様性だと言えるのではないでしょうか。“取得率”という数字だけでなく、“自分自身で選んだ”という背景にも目を向けることが大切だと私たちは認識しています」。

取得しやすい文化は、人から人へ伝播して醸成される。
強制力のあるルールを設けないからこそ、育業を取得したい人が、あたり前に取得できる仕組み・雰囲気づくりがいっそう重要となる。男性育業の社内浸透のために、これまで行なってきた具体的な取り組みについても伺った。
「制度面での取り組み例としては、2005年に導入した『育児休業の一部有給化』が挙げられます。当時は世の中でも男性の育業(育休)は一般的ではなかったのですが、収入面での不安を少しでも解消し、取得推進につなげられればと策定いたしました」。
男性育業を認知・理解してもらう施策では、社内報『森永ライフ』内にて、制度の紹介や取得者の声などを掲載し全従業員に配布した。メールや書面だけでの通達では、読み飛ばされることが多いが、写真や図をあしらった冊子にすることで社内からの反響が大きかったという。さらに男性育業の浸透のために最も欠かせないのが、「人から人に伝わる温度感」であると高橋さんは続ける。
「やはり制度があることを知っているだけでは、実際の行動に移せない人もいます。だからこそ、出産を控える従業員に対して、上司や先輩から声がけをすることが大切だと考えています。具体的な制度の説明でなくても、『おれが取得したときは…』『妻が喜んでくれてね』といった話で良いと思いますね。そうした何気なくも温度感のあるリアルな話が、育業取得の後押しになるものです。そして今度は取得者が、自分の体験談を後輩たちに話してくれる。このような人から人への伝播が、育業を取得しやすい文化を醸成するのだと考えています」。
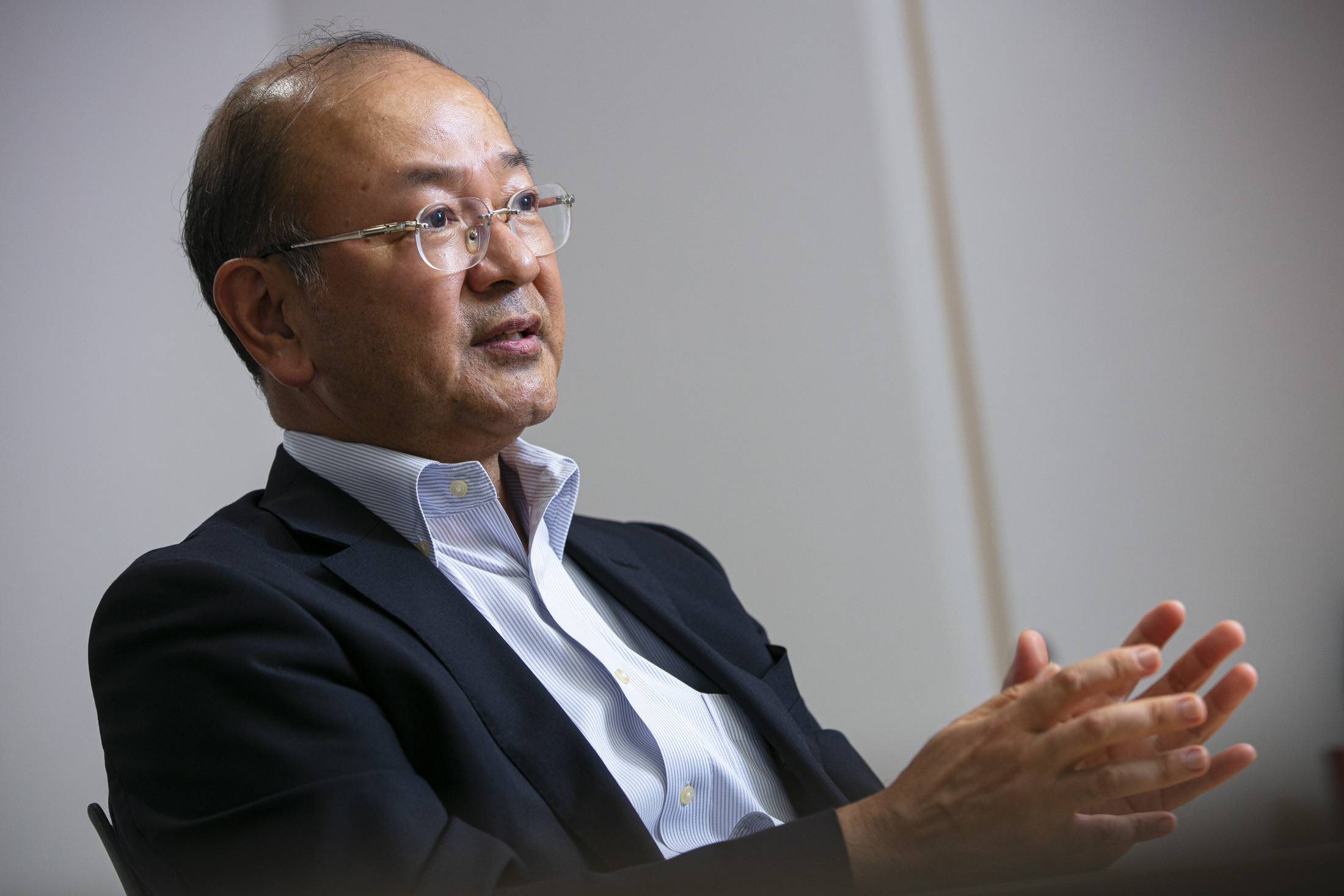
男性育業を個の自律、そして経営戦略へとつなげる。
森永製菓では人材開発の基本方針のひとつとして、「個人のキャリア自律」を掲げている。従業員がキャリアについて自分なりの考えを持ち、自身の力でキャリアを切り拓くことを奨励し、その実現に向けたサポートを惜しまないのが同社の姿勢だ。
「『キャリア』の定義は、どんな仕事をどこの部署で行なうということや、上位職に就くといったことに限りません。それぞれの価値観から、自分の生きがいや生きかたを見出し、どんな人生を歩んでいくかがキャリアの本質だと言えるでしょう。そういった意味では、大きなライフイベントである出産の時期をどう捉え、どう過ごしたいかを自分で選択することも『個人のキャリア自律』につながると考えています。そして、育業を取得する・しない、取得期間の長短に関わらず、幅広い選択肢を提示することが会社としての役割だと思っています」。
今後、当社がさらに人的資本経営を実践していく中で最も重要なのが、個人のキャリア自律によって、ポテンシャルを最大限に引き出すことだと考えていると、高橋さん。
「男性の育業取得という機会・制度を独立して捉えるのではなく、個人のキャリア自律の一助に、ひいては経営戦略の実現にもつなげていければと思います。そして、男性育業に限らず、あらゆる面で従業員にとっての選択肢が多い組織形成を目指していきたい」そう高橋さんは締め括った。