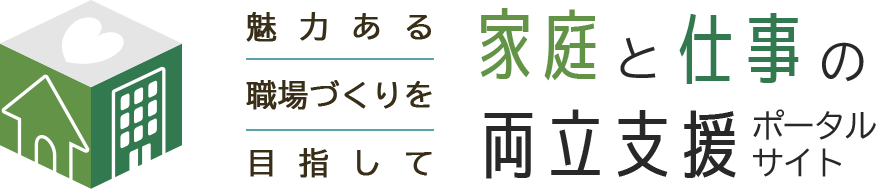- HOME
- 介護と仕事の両立
- 東京都の施策、調査等
- 介護と仕事の両立推進シンポジウム
- 「令和6年度 介護と仕事の両立推進シンポジウム(企業経営者・人事労務担当者向け)」講演要旨
「令和6年度 介護と仕事の両立推進シンポジウム(企業経営者・人事労務担当者向け)」講演要旨
1 開催日時:令和6年11月5日(火曜日)13時30分~16時30分
2 開催形式:オンライン(Zoomウェビナーを利用したライブ配信、2か月程度のオンデマンド配信)
3 定員:200名
4 内容:
【基調講演】
「企業による仕事と介護の両立支援 介護離職を防止する仕組みづくり」
和氣美枝氏(一般社団法人介護離職防止対策促進機構代表理事)
これから、企業における仕事と介護の両立支援、および介護離職を防止するための仕組みづくりについて、育児・介護休業法の改正内容を踏まえながら解説いたします。私自身20年にわたり介護と仕事を両立してきた経験を持ち、介護離職防止対策促進機構の代表理事として、政策提言や人材育成に取り組んでいます。
仕事と介護の両立支援が必要とされる背景について、令和4年の就業構造基本調査によれば、日本の全有業者6,706万人のうち、働きながら介護をしている者は364万人に上る、とされています。介護はいつ始まるかわからず、誰もが当事者になり得るため、介護離職防止対策の対象は介護に直面している者に限らず、すべての有業者に広がることになります。企業がこの問題に取り組むことは、単なるケア支援ではなくキャリア支援であるという事も忘れたくありません。
育児・介護休業法の改正については3つの柱があり、いずれも事業主に新たな義務を課すものです。第一に、介護に直面した労働者に対する個別周知と意向確認の義務ですが、従業員が介護の状況を申告した際に、介護休業や介護両立支援制度の内容を適切に周知し、意向を確認することを求めるものです。特に、介護休業は直接的な介護のための制度ではなく、介護の準備や体制づくりのための一定期間の休業であることを明確にされています。
第二に、40歳を迎える労働者に対して、介護と仕事の両立支援に関する情報提供を行うことが義務化されました。40歳という年齢は、介護に直面する可能性が高まる時期として設定されており、情報提供の手段や内容についても詳細に規定されており、企業が単なる通達ではなく、計画的かつ適切な方法で周知を行うことが求められることになります。
第三に、研修や相談窓口の設置など、雇用環境の整備の義務化も改正点です。具体的には、介護支援制度に関する研修の実施、社内相談窓口の設置、制度利用の事例紹介、制度利用促進のための方針の周知などです。特に相談窓口については、従業員の家庭の介護状況に関する相談を受ける場ではなく、あくまで介護休業や両立支援制度に関する相談窓口である点が強調されました。
また、企業には努力義務として介護期におけるテレワークの導入を検討することが求められています。ただし、在宅勤務と在宅介護は異なる概念であり、適切なガイドラインを作成し、従業員が業務に集中できる環境を整えなくてはなりません。加えて、従来、勤続6か月未満の労働者は介護休暇を取得できない、という制限が撤廃され、入社直後でも介護休暇を取得できるようになりました。
仕事と介護の両立支援の本質について、介護を理由に仕事を辞めることが選択肢とならないよう、企業が労働環境を整備することが求められています。介護離職を防ぐためには、従業員が介護に直面する前から支援を受けられる仕組みを構築し、介護が始まった際にも、仕事と介護のバランスをとりながら生活を維持できる環境を作ることが重要です。企業の支援がなければ、従業員のキャリアが断絶し、企業にとっても貴重な人材の喪失につながってしまうでしょう。
企業の介護離職防止対策は、単なる福利厚生ではなく、戦略的なキャリア支援の一環である点も強調されました。従業員の介護離職は企業にとっても経営課題であり、従業員の介護離職を防ぐことは、長期的な人材確保にもつながります。企業が従業員の仕事と介護の両立を支援することで、従業員の安心感や職場への信頼が向上し、結果として企業の生産性や定着率の向上にも寄与することができます。
最後に、介護は突発的に始まり、長期化する可能性が高いため、企業側は長期的な視点で従業員を支援しなければならないという事を再度強調いたします。企業にとっての介護離職防止対策は、単なる社会的責任ではなく、人材戦略の一環であり、適切な支援を行うことで企業と従業員の双方にメリットをもたらすものです。是非、企業は仕事と介護の両立を支援するために取るべき具体的な施策を理解し、実践へとつなげる様にしてまいりましょう。
企業取組事例発表①
経営の観点から考えた、不動産ベンチャーの介護離職防止策と導入経緯について
株式会社アットオフィス
代表取締役社長CEO谷健太郎氏
株式会社アットオフィスはオフィス移転仲介を中心とした事業を展開しており、主にスタートアップやベンチャー企業を対象としています。不動産業界では珍しく、平均年齢が29歳と非常に若い組織であり、私も33歳と若い経営者です。そのため、一般的には介護の問題とは距離があると思われがちですが、実際にはそうではなく、若い世代であっても介護離職の問題を身近に捉えるべきだと感じています。
同社が介護離職防止のために行っている取り組みとして、大きく2つの施策を持っています。1つ目は「介護離職防止セミナー」の開催です。これは全社員を対象としたもので、少なくとも年に一度は「介護離職」という概念に触れる機会を提供しています。営業職が多く、全員がリアルタイムで受講することは難しいですが、未受講者には翌年の受講を促すなどの対応を行い、確実に知識を浸透させるよう努めています。2つ目は「相談窓口の設置」です。社員が気軽に相談できるように、Googleフォームを活用した匿名の相談窓口を社内イントラネット上に設けました。直接経営層に申し出ることが難しい社員でも、テキストを通じて相談できる仕組みとし、その後、必要に応じて専門家と連携する体制を整えました。
私がこの問題に関心を持つようになった背景には、2つの大きな要因があります。1つ目は、私の祖母が認知症になった経験です。介護の負担は計り知れず、特に家族が1人で担う場合は精神的・肉体的に大きな負担となります。さらに、介護は突然訪れるものであり、誰もが当事者になり得るという気づきを得ました。この経験を通じて、若い世代であっても決して無関係ではないという意識を持つようになりました。2つ目の要因は、統計データに基づく合理的な判断です。少子高齢化が進み、採用がますます困難になる時代において、企業は既存の社員をいかに活用し、働き続けてもらうかが経営の重要な課題となります。そのため、介護離職を防ぐ取り組みは、中小企業こそ積極的に行うべき施策であると考えるに至りました。
実際にこれらの施策を導入した結果、同社の20代の社員の中にも介護を抱える人がいることが判明しました。具体的には、社員数約80人のうち2名が介護中だったそうです。これは発生率にして約2.5%に相当し、中小企業であっても決して無視できない数字です。この発見により、「会社に相談してもよいのだ」と社員が認識し、介護に直面した際の心理的な障壁を取り除くことができました。単に就業規則に介護制度が存在するだけでは不十分であり、経営層が関心を持ち、発信し続けることが、社員が安心して相談できる環境づくりにつながると実感しました。
今後の課題としては、経営層と社員との信頼関係をより強化し、相談しやすい雰囲気を醸成することです。施策の導入だけでは不十分であり、「相談すれば何かしらの解決策が見つかる」と社員が実感できるような環境を構築することが不可欠です。そうした信頼関係の積み重ねが、介護離職を未然に防ぐ鍵になるのではないでしょうか。
最後に、特に中小企業の経営者は「0を1に変えること」が重要ではないかと考えます。介護問題に関する知識や、相談できる仕組みを社内に持たない企業は多いです。しかし、最初の一歩を踏み出すことが、社員の安心感につながり、結果的に企業の持続的成長にも寄与します。大規模な投資をせずとも、セミナー開催や相談窓口の設置といった小さな取り組みから始めることが可能であり、それが企業の競争力強化にもつながるのではないでしょうか。
企業取組事例発表②
多様な人財の活躍に向けた「介護と仕事の両立」の取組み紹介
アフラック生命保険株式会社
ダイバーシティアンドインクルージョン推進部課長 横尾真紀子氏
アフラックは1974年に創業した生命保険会社であり、1985年には世界で初めて民間の介護保険を提供した企業でもあります。当社は、社会的課題の解決を通じて社会と共有できる価値を創出する「CSV経営」を経営戦略の一環として掲げており、2024年までの中期経営戦略において「人材マネジメント戦略」を最重要課題と位置づけています。その中で、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)や働き方改革(アフラック ワークスマート)を推進しています。介護と仕事の両立支援については、2017年から本格的に取り組みを開始しました。その背景には、2016年の全社意識調査で、5年以内に介護に直面する可能性が高いと回答した社員が約4分の1に上り、さらに60%近くの社員が「介護に直面したら働き続けられるか不安」と感じていることが明らかになったことがあります。この結果を受け、当社では介護前、介護中、介護後の各フェーズに分けて支援策を整備しました。
具体的な取り組みとして、まず「知識の提供」が挙げられます。セミナーの開催やイーラーニングの実施、両立ハンドブックの提供を通じて、介護に関する基本的な知識や心構えを社員に伝えています。特にセミナーでは、専門家や介護経験者を招き、実践的なアドバイスを提供しています。次に「当事者支援」として、介護中の社員や介護経験者が情報交換を行う「介護コミュニティ」を2019年に設立し、定期的なミーティングを実施しています。さらに、グループ会社を通じて介護に関する相談窓口を設け、介護前から介護後まで継続的なサポートを提供しています。
また、働き方改革の一環として、テレワークやフレックスタイム制度を全社員に導入し、時間と場所に縛られない柔軟な働き方を推進しています。これにより、介護と仕事を両立する社員の環境整備が進んでいます。これらの取り組みの結果、介護に直面した際に働き続けられるか不安を感じる社員の割合は減少し、ライフイベントがあっても長く働き続けられる会社だと感じる社員の割合は増加しています。
しかし、課題も残されています。一つは、介護に関する知識が不足している社員が7割以上いることです。知識を身につけるだけでなく、それを自分事として捉えることが重要です。もう一つの課題は、職場や上司の理解とサポート体制の構築です。実際に介護をしている社員の30%が上司に相談しておらず、40%以上が職場に迷惑をかけていると感じていることが明らかになっています。今後は、介護と仕事の両立支援が日本企業全体で当たり前になることを目指していきたいです。
企業取組事例発表③
コロナ禍~コロナ明け後の取組と支援体制の強化
株式会社はなまる
はなまる管理部 LWB委員会 ケア×ケアチーム 角田映子氏
株式会社はなまるは、セルフ式うどん店の直営店舗運営およびフランチャイズ事業の開発を主な事業として展開しています。こうした事業の特性上、店舗勤務者が多く、介護と仕事の両立において特有の課題を抱えています。
同社における介護支援活動は、もともと女性活躍推進の取り組みから発展したものです。2007年に「HLPJ(Hanamaru Ladies Project)」が発足し、女性が働きやすい職場環境の整備を目的とした活動が始まりました。その後、2009年に公式組織となり、2015年には男性社員も参画する形で組織改革が行われました。この際に「ケアラー支援プロジェクト」が立ち上げられ、介護と仕事の両立を支援する活動が本格的に始動しました。2017年には「ライフワークバランス(LWB)推進部」として活動を拡大し、社内での意識改革を進めました。しかし、2020年のコロナ禍により一時的に活動を休止せざるを得ませんでした。2023年のコロナ収束後、LWBの活動が再開されると、新たに「ケア×ケアチーム」として介護支援とメンタルケアの両面からのサポートを行う体制が整えられました。そして、2024年には「LWB委員会」として組織を再編し、より継続的な支援活動を推進しています。
同社が介護支援活動を開始した背景には、私自身の経験が大きく関与しています。出向と同時期に家族の介護が重なり、情報不足の中で施設利用や相談窓口の選択に苦慮しました。特に遠距離介護という状況の中、慣れない職場での長時間労働と週末の介護が続いたことで、精神的・肉体的な負担が増大し、離職を考えるほどの状況に陥りました。しかし、情報収集を進めるうちに地域包括支援センターへたどり着き、適切な手続きを経て介護サービスを利用することで、離職を回避することができました。この経験から、同様の困難に直面する従業員を支援する必要性を強く感じ、2015年に「ケアラー支援プロジェクト」を立ち上げるに至りました。本プロジェクトでは、社内周知活動の強化、専門講師によるセミナーの実施、介護離職防止対策アドバイザーの資格取得による社内研修の内製化、グループ会社への活動波及といった施策を展開しました。さらに、従業員同士が介護について気軽に話し合う場として「ケアバル」を実施し、現場で働く従業員の意見を直接聞く機会を設けました。このように、介護と仕事の両立を支援するための施策を多角的に実施してきました。
しかし、2020年のコロナ禍により、これらの活動は大きく制約を受けました。会社存続を優先する業務体制への移行に伴い、リアルセミナーや対面相談は中止せざるを得ませんでした。その一方で、オンライン相談窓口を継続し、社内ツールを活用したWEBセミナーを実施することで、可能な範囲で支援を継続しました。コロナ禍においては、「施設利用や病院面会が制限され、看取りができなかった」「保育所閉鎖により育児と介護の両立が困難になった」「遠距離介護で移動が制限された」といった深刻な声が多数寄せられました。このような状況を受け、企業としての支援策を改めて見直す契機となりました。
2023年のLWB再稼働を機に、支援活動をより強化し、新たなメンバーを公募して取り組みを拡充しました。特に、営業部を中心とした支援活動を強化し、店長や管理職を対象とした研修を徹底しました。店舗勤務者が多い飲食業の特性を踏まえ、店長およびエリアマネージャーを対象とした研修を実施し、リアルセミナーを再開しました。前回のセミナーから約5年が経過し、その間に親の介護が始まった従業員も多く、「もはや他人事ではない」という声が多く聞かれました。さらに、「ケアバル」の再開を決定し、従業員が介護について率直に話し合える環境を整えることとしました。
今後の課題として、勤務時間の柔軟な調整が難しい飲食業において、店長やエリアマネージャーが介護に直面した際の対応が挙げられます。勤務地変更の柔軟な対応、介護期間中の業務負担軽減措置、介護休暇制度の拡充について、具体的な施策を検討する必要があります。特に、現在正社員に適用されている年間5日間の有給介護休暇について、非正規スタッフにも適用する方向で調整を進めています。
さらに、2025年の育児・介護休業法改定に向けて、各拠点に支援担当者を配置し、介護者の声を迅速に拾い上げる体制を構築する予定です。また、社内コミュニティを強化し、介護に関する悩みを共有できるWEBツールを導入することで、介護者の孤立を防ぎ、介護離職の防止を図ることを目指しています。
最後に、周知活動の継続が極めて重要であることを改めて強調します。介護と仕事の両立を支援するためには、社内全体に対する意識改革が不可欠であり、周知活動を継続的に行うことで、支援策の定着を図っていく必要があります。介護に関する課題は一過性のものではなく、今後も継続的な取り組みが求められるため、社内の意識を高め、支援体制を強化し続けることが不可欠です。
トークショー
「仕事と介護の両立支援 隠れ介護者と心理的安全性の担保について」
駒村多恵氏(フリーキャスター/介護福祉士)× 和氣美枝氏(一般社団法人介護離職防止対策促進機構代表理事)
和氣:本日は「仕事と介護の両立支援」「かくれ介護者と心理的安全性の確保」というテーマで、駒村さんとお話を進めていきます。
駒村:現在、要介護5の母を介護しており、介護を始めてから17年になります。フリーキャスターとして、NHKの「あさイチ」など情報番組に出演し、長年、生放送を担当してきました。生放送は時間管理が厳しいですが、終わりが決まっているため、介護との両立には向いている面もあります。 介護が始まった当初は、どうやって両立すればいいのか全くわかりませんでした。私は32、3歳の頃、忙しく仕事をしていた中で、母の介護が必要になりました。しかし、当時は周囲に介護をしている人がいなかったため、相談相手もいませんでした。自治体の体操教室やアクティビティに参加させ、日中独居を防ぐよう工夫しました。しかし、時間が経つにつれて母が転倒することが増え、いよいよ要介護認定を受けることになりました。介護のステージが上がると、仕事への影響が大きくなります。生放送中でも病院や施設からの電話が頻繁にかかってきて、リハーサルの合間に対応しなければならず、何度も折り返しのやりとりが発生しました。特に病院の初診や入院手続きには家族の付き添いが必要で、仕事との調整が非常に難しかったです。私はヘルパーさんに付き添いをお願いし、診察のタイミングで駆けつけるなどの工夫をして乗り越えてきました。
和氣:そうした状況の中で、職場にはいつ頃、介護のことを伝えたのでしょうか?
駒村:最初の数年間は、職場の誰にも介護のことを話しませんでした。実際、ある管理職の方が「出産直後の女性には仕事を発注しないほうがいい」と判断したケースを見て、「介護も同じことが起こるのでは」と感じたからです。介護を公にすると、仕事の機会が減るのではないかという不安がありました。 しかし、仕事との両立が難しくなり、上司に相談するようになりました。すると、次第に「駒村さんの家は介護が必要なんだな」と周囲に認識され、雑談の中で介護の話をすることも増えました。結果として、仕事の調整がしやすくなり、介護の負担も軽減されました。また、コロナ禍を経て、オンライン対応が進んだことも大きな変化です。オンラインで仕事ができる環境が整い、介護をしながらも持続可能な働き方が実現しやすくなりました。さらに、周囲のサポートを受け入れることの重要性も実感しました。自分一人で抱え込むのではなく、ヘルパーさんやケアマネージャーを活用することで、介護と仕事の両立がしやすくなります。
和氣:介護をオープンにすることで、周囲の理解を得られ、負担が軽減されたのですね。管理職の立場としては、どのようなサポートが求められると思いますか?
駒村:まず、介護をしている社員が「話せる環境」を整えることが重要です。介護者は「迷惑をかけたくない」という気持ちから、周囲に話しづらいことが多いです。しかし、不安を抱えたまま仕事を続けると、パフォーマンスにも影響が出ます。管理職の方には、介護者が安心して相談できるような雰囲気づくりをお願いしたいです。 また、仕事を発注する際は「できますか?」と聞いてほしいですね。できる場合は引き受けますし、難しい場合は断る選択肢があれば負担になりません。介護の状況は変化するため、柔軟な対応が求められます。 現在の私の状況としては、社会資源をフル活用し、仕事中は介護を忘れて集中できる環境を整えました。その結果、仕事と介護の両方にやりがいを持って取り組めています。
和氣:本当に貴重なお話をありがとうございます。介護と仕事を両立するための具体的な工夫や管理職の役割について、非常に参考になりました。