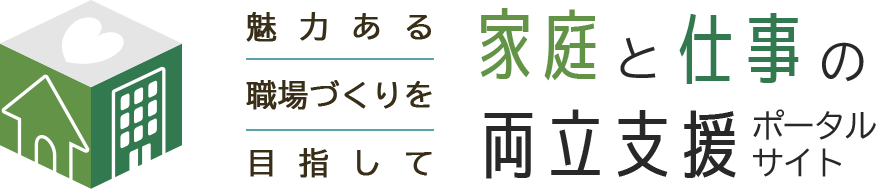- HOME
- 介護と仕事の両立
- 東京都の施策、調査等
- 介護と仕事の両立推進シンポジウム
- 「令和6年度 介護と仕事の両立推進シンポジウム(従業員向け)」講演要旨
「令和6年度 介護と仕事の両立推進シンポジウム(従業員向け)」講演要旨
1 開催日時:令和6年11月6日(水曜日)13時30分~16時30分
2 開催形式:オンライン(Zoomウェビナーを利用したライブ配信、2か月程度のオンデマンド配信)
3 定員:200名
4 内容:
【基調講演】
「突然の介護!上手な備え方・働き方の3つのステップ 人生をあきらめないために大切なこと」
丸山法子氏(リエゾン地域福祉研究所 代表/社会福祉士/介護福祉士)
介護に対するイメージは、一般的にネガティブなものが多いです。しかし、実際には介護は人生の一部として誰にでも起こり得るものであり、適切に理解し準備することが求められます。加齢に伴い、身体機能や認知機能が低下することは避けられませんが、その変化には個人差があり、90代になっても元気に生活する人もいます。一方で、多くの人は60代・70代から徐々に自立度が低下し、医療や介護の必要性が高まります。厚生労働省の統計によると、生涯医療費は約2800万円であり、その半分が70歳以降に使われるとされています。これは、後期高齢期における医療・介護のニーズの増加を示しています。また、要介護の原因として、男性は脳血管疾患や生活習慣病、女性は認知症や骨折・転倒が多いです。認知症は今や珍しい病気ではなく、6人に1人が予備軍とされています。認知症の進行を抑える治療法や、認知症の人が働ける環境も整備されつつありますが、依然として家族や社会のサポートが不可欠です。
要介護の進行には、大きく「心身の衰え」と「認知能力の衰え」の2つがあります。心身の衰えはフレイル(虚弱)と呼ばれ、日常生活の基本動作(ADL)の低下によって表れます。例えば、歩行や食事の準備、買い物などが難しくなり、やがて介助が必要となります。一方、認知能力の低下は、記憶力や判断力の衰えとして現れ、道に迷う、言葉が出てこないといった症状が見られます。これらの能力が低下すると、日常生活を自立して送ることが難しくなり、家族や周囲の支援が不可欠となります。
介護はかつて家族、特に女性の役割とされていましたが、現在では社会全体で支えることが求められています。介護の担い手としては、家族、専門職、近隣住民や知人、さらには社会サービスが挙げられます。家族による介護は依然として多いですが、一人暮らしの高齢者が増加する中で、家族だけでの介護には限界があります。また、「ハチマル・ゴーマル」世帯(80代の親と50代の未婚の子の2人暮らし)や、育児と介護を両立するダブルケアラー、介護を担うヤングケアラーの問題も深刻化しています。介護を理由に進学や就職を諦める若者も多く、社会全体での支援が求められます。専門職による支援としては、介護福祉士や理学療法士、作業療法士、医師、歯科医師などが挙げられます。これらの専門家の技術を活用することで、家族だけでは対応が難しい場面でも適切なケアが可能となります。しかし、介護人材の不足が進んでおり、地方では介護サービスの廃業も相次いでいるため、持続可能な介護体制の構築が課題となっています。近隣住民や知人、友人のネットワークも重要な役割を果たします。町内会や自治会、民生委員の協力を得ることで、高齢者の見守りや日常生活の支援が可能となります。さらに、調理や掃除、外出の付き添いなどを提供する地域のサービスも拡充されており、これらを上手く活用することが求められます。
介護と仕事を両立するためには、事前の準備が欠かせません。介護は突然始まることが多いため、あらかじめ情報を収集し、適切な備えをしておくことが重要です。まず、介護保険制度や地域の介護サービスについて学び、必要なときにどのような支援が受けられるのかを把握しておくことが求められます。特に、介護休業制度や短時間勤務制度など、仕事と両立するための制度について理解を深めることが大切です。また、地域包括支援センターや地域医療連携センターなどの専門機関を活用し、医療費を含めた相談を行うことも有効です。
次に、家族間での話し合いを事前に行うことが必要です。介護が必要になった際にどのような対応を取るのかを家族で共有し、親の希望を確認しておくことが望ましいです。「どこで暮らしたいのか」「どのような介護を望むのか」といった意思を早めに確認し、具体的な計画を立てることが大切です。事前に話し合っておくことで、介護が必要になった際に家族内での意見の食い違いを減らし、スムーズな対応が可能になります。
さらに、職場との調整も重要な準備の一つです。介護が始まった際に柔軟な働き方ができるよう、職場と相談し、活用できる制度について確認しておくことが望ましいです。介護休業や時短勤務などの制度を利用することで、仕事と介護の両立がしやすくなります。また、介護離職を避けるためにも、職場の理解を得ながら働き方を調整することが必要です。介護による経済的負担を軽減し、将来的な生活の安定を確保するためにも、早めの準備が求められます。
介護は特別なものではなく、誰にでも訪れる可能性があります。適切な準備を行うことで、介護による負担を軽減し、仕事との両立を図ることが可能となります。家族だけで抱え込まず、専門職や地域の支援を活用しながら、介護を前向きに捉えることが重要です。また、介護は親の問題だけでなく、自分自身にも関わるものであるため、40代・50代のうちから備えておくことが望ましいです。 本講演では、介護の全体像と課題を理解した上で、介護と仕事を両立するための準備の重要性が強調されました。参加者の皆様には、介護を「突然の出来事」ではなく、「計画的に準備するもの」として捉え、今後の生活設計に活かしていただきたいと考えております。
従業員体験談紹介①
ひとりにしない介護 社員同士で支えあうコミュニティ「介護ラボ」のご紹介
NTTテクノクロス株式会社
営業推進部 R&D クロスリレーション部門 奥雅博氏
私の勤めているNTTテクノクロスはNTTグループのICT企業であり、従業員の平均年齢が45歳以上と比較的高齢化が進んでいます。昨年度の社内アンケートによると、14%の社員が現時点で主な介護者であり、61%が今後5年以内に介護を担う可能性があると回答しており、介護は避けて通れない課題となっています。NTTテクノクロス株式会社では、在宅勤務制度やスーパーフレックス制度を導入し、介護者が仕事と両立しやすい環境を整備しています。これにより、勤務の柔軟性を高め、短時間勤務や時間外労働の制限などの施策を通じて、社員が介護負担を軽減できるよう配慮しています。私自身、大阪の実家で一人暮らしをしていた母親の介護を担うことになり、最初はご近所の支援を頼りにしていましたが、脳梗塞や骨折を機に神奈川へと呼び寄せました。しかし、環境の変化が認知症の進行を加速させたと感じ、在宅介護の困難さを痛感しました。その後、幸運にもグループホームに入所できましたが、入所後に健康状態が悪化し、最終的に病院での治療を経て亡くなりました。介護を終えた後も、施設入所時の安堵感に罪悪感を抱いたり、認知症の進行を防ぐために大阪で介護すべきだったのではないかと後悔が残るといいます。しかし、職場の理解や支援があったことで、精神的な負担を軽減できました。
NTTテクノクロス株式会社では2020年12月に「介護ラボ」を立ち上げました。これは、介護を重要課題と認識した社員が主体となっている、会社公認のコミュニティです。介護経験者、現役介護者、介護に関心のある社員が集まり、情報共有や相談の場を提供しています。介護ラボの目的は、社員が気軽に相談できる職場環境を整え、支援体制を構築することです。具体的な取り組みとして、社内ホームページでの情報発信、介護セミナーの開催、専門家を招いた意見交換会を実施しています。さらに、職場全体で介護を自分ごととして捉え、支援意識を醸成するために「介護事例共有会」を開催し、社員同士が自身の介護経験を語り合う機会を設けています。介護と仕事の両立には、介護者自身が適切にリフレッシュし、周囲の助けを得ることが不可欠です。また、介護に関わる家族や親族との協力を確認し、役割を明確にすることも重要です。加えて、介護が終わった後の自分の生活を考え、離職を防ぐために職場の支援を活用することが求められます。
NTTテクノクロス株式会社の行動指針「CROSS」(チャレンジ、リスペクト、オープン、シナジー、スマイル)に基づき、介護に取り組む社員とその家族をリスペクトし、支援を行い、職場全体で相互に助け合う文化を醸成することが重要であると実感しました。介護ラボは、社員が安心して介護と仕事を両立できる環境を整備するため、今後も活動を継続していく方針です。
従業員体験談紹介②
介護は“お互い様”の気持ちで、社員を支える人事制度の活用事例
大成建設株式会社
人事部 人財いきいき推進室 国枝愛奈氏
大成建設株式会社では、介護を「お互いさま」の気持ちで捉え、直面した際にも柔軟に制度を活用して働いている社員が多くいます。本日は、当社の取り組み方針と両立支援制度、および活用事例を紹介します。
介護に対する当社の取り組み方針についてですが、介護は個別性が高く、個々の事情に応じた対応が非常に難しいと感じています。そこで、仕事と介護の両立を支援するため、「情報提供」と「お互い様精神の風土醸成」に取り組んでいます。情報提供の一つとして、ケアマネージャーと相談する際に活用できるリーフレットを用意しています。左側に当社の両立支援制度を記載し、右側には社員の働き方や健康状態、希望する介護について記入できる欄を設けています。
介護に対する不安を解消する目的で、全社員およびその家族を対象にした介護セミナーを提供しています。セミナーでは、介護が始まる前の準備や心構え、施設選び、介護保険制度、認知症、遠距離介護など、毎回異なるテーマで情報提供を行っています。さらに、心的負担の軽減を目的として、40歳になった社員に「介護のしおり」を配布し、複数の相談窓口を設置して案内を行っています。また、お互い様意識の醸成の一環として、社長メッセージを社内報で発信し、両立支援の取り組みを紹介しています。加えて、介護に直面した社員が安心して上司に相談できるよう、上司向けのセミナーを開催し、サポートを行っています。
続いて、当社の両立支援制度を紹介します。介護とは、食事や入浴の世話などの身体介護に限らず、通院付き添いやケアマネージャーとの面談、介護施設の見学など、生活全般を支える行為全てを含みます。そのため、仕事を休まざるを得ない日が生じることもあります。そこで、介護に伴う休暇を取得できる支援制度として、「介護休業」「介護休暇」「失効年金の積立休暇」などを用意しています。介護休業は、要介護者1名に対して年15日、2名以上の場合は20日付与しています。半日単位や時間単位での取得も可能です。失効年金の積立休暇は最長80日まで取得可能で、半日単位での利用が認められています。すべて有給休暇として取得できます。介護休暇の利用状況については、2023年の介護休暇取得者数が、男性123名、女性118名でした。年齢別では、40代以下が37名、50代が126名、60代以上が78名で、計241名が利用し、平均取得日数は6日でした。介護休暇は、1日単位よりも通院付き添いや行政手続きなどのために数時間単位で取得するケースが多いです。一方、介護休業は給与が減ることもあり、年間1名程度の利用にとどまっています。今年1月からは、介護でも両立支援フレックスを活用できるようになりました。
続いて、当社の社員による介護の活用事例を紹介します。
別居介護をする50代男性(事務職)。介護休暇と介護セミナーを活用し、身体障害のある父親と認知症の母親の介護と仕事を両立しました。介護セミナーを受講し、地域包括支援センターを活用することでスムーズに介護初動期を乗り切りました。
別居遠距離介護をする50代男性(設計職)。介護セミナー、介護休暇、当社提携の「海を越えるケアの手」を活用しました。ケアマネージャーとの関係やケアプランでの悩みを解消し、納得のいくケアを実現しました。
多重介護をする50代女性(営業職)。80代の両親と祖母の介護を両立しました。介護休暇を活用し、業務関係者との調整を綿密に行いながら対応しました。
医療的ケアが必要な子どもを育てる30代男性(作業所勤務)。介護休暇制度を活用し、同僚や職人にも事情を伝え、職場全体の理解を得ました。介護の始まりは出産時13トリソミー、染色体異常症とわかり、NICUに半年入院しました。現在は在宅ケアをしています。無呼吸発作があるため気管切開をしており、痰の吸引は欠かせず、呼吸管理も必須で常時見守りが必要です。子どもが13トリソミーとわかった時点で上司に報告し、同僚や職人にも雑談や日常会話の中で事情を伝えました。その結果、「実はうちも…」と家族の病気の話を打ち明けてくれる人もおり、親近感を持って接してくれるようになりました。職場全体の雰囲気も柔らかくなり、結果的に皆が働きやすい職場になったと話していました。
心疾患のある配偶者を介護する40代男性。介護休暇を前日・半日・時間単位で柔軟に活用しました。直属の上司だけでなく、関係部署の上長にも相談し、周囲の協力を得ました。
介護は誰にでも起こり得ます。上司や会社の相談窓口、病院、行政などに相談することから始めることが大切です。周囲の協力なしには介護の両立は困難なため、互いに支え合う社会を構築していきたいと考えています。
トークショー
「介護を一人で抱え込まないために」
丸山法子氏(リエゾン地域福祉研究所 代表/社会福祉士/介護福祉士)× ハリー杉山氏(タレント)
丸山:本日のトークショーでは「介護を一人で抱えないために」をテーマに、仕事をしながら介護を経験したハリー杉山さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
杉山:よろしくお願いします。私はイギリス人の父と日本人の母のもとに生まれ、日本とイギリスで育ちました。22〜23歳頃から芸能活動を始め、現在はテレビやラジオで活動しながら、介護の経験についても発信しています。
丸山:早速、介護のお話をお伺いしたいのですが。
杉山:私の介護の経験は、祖母の脳梗塞から始まりました。祖母は2011年に発症し、半年後に亡くなったのですが、今度は2015年頃、父がパーキンソン病と認知症を発症しました。父はエリートジャーナリストで私の憧れの存在でしたが、病気が進行するにつれ、介護の大変さを痛感しました。介護の知識がなかったため、初めは適切な対応ができず、父が混乱して暴れたり、在宅介護が難しくなったりしました。仕事と介護の両立も困難で、常にスマホを持ち、仕事中も緊張していました。最終的に介護施設の力を借りることになりましたが、それでも定期的に訪問し、リハビリをサポートしました。
丸山:介護の負担は大きいですよね。
杉山:はい、一人で抱え込むと心身ともに限界がきます。介護の知識を持つこと、専門家の力を借りること、そして仕事とのバランスを考えることが大切です。自分が倒れてしまっては意味がありません。介護を「一人でやるもの」と考えず、周囲と協力しながら進めることが重要です。
丸山:パーキンソン病だと歩くのがどんどん難しくなりますよね。
杉山:そうなんです。関節が固くなって転倒のリスクも高まります。でもリハビリを通じて自信を持ってもらうことが大切で、やる気を失わないように工夫するんです。例えばマッサージをして、好きな音楽を聴かせて、ようやくやる気が出ることもあります。
丸山:家族との時間を作ることも大事ですよね。小さな思い出作りでも、コーヒーを飲みに行くとか、旅行に行くとか。そういう時間を支えてくれる介護のプロがいるのも大きいですね。
杉山:そうです。介護施設や市役所の方々の支えがあれば、介護を受ける人の人生も豊かになりますし、家族も今までより深い話ができるようになることもあります。僕も父と会うたびに「これが最後かもしれない」と思っていました。
丸山:その覚悟を持つまでに大変な道のりがあったでしょうね。仕事と介護の両立も難しかったのでは?
杉山:かなり大変でしたね。在宅介護を始めたのが26~27歳の頃。周りの友達は仕事や遊びに忙しくて、僕の悩みを話せる相手がいませんでした。でも、ケアマネージャーさんとの出会いが大きかったです。その方のおかげで「仕事を諦めなくていい」と思えました。
丸山:いい出会いでしたね。
杉山:本当にそうです。介護をひとりで抱え込まず、専門家に頼ることが大事。プロの力を信頼すれば、自分も仕事に集中できますしね。
丸山:でも実際は、介護に直面してもどこに相談すればいいかわからない人が多いですよね。
杉山:そうなんです。大切な人が弱っていく姿を認めたくないし、外に見せたくない気持ちもある。でも、介護を全部自分たちでやろうとすると心も体も限界がきます。僕も母も疲れ果ててしまって、家の壁に穴を開けるほど追い詰められたこともありました。
丸山:壮絶ですね。被介護者を殴ってしまった人を知っているんですが、それだけ介護者は追いつめられるという事なんですね。
杉山:僕も一歩手前までいきました。父に突き飛ばされたり、ご飯を食べてもらえなかったりすると、どうしようもなくなる。だけど、プロの介護サービスを受けるようになって、そういう日々はなくなりました。
丸山:最初から適切なサポートを受けていれば、状況は違ったかもしれないですね。
杉山:本当にそう思います。最初は「自分たちでやる」という気持ちが強すぎた。でも、プロの知識やサポートを受け入れることで、介護する側もされる側も穏やかに過ごせるようになるんですよね。
丸山:認知症の場合は早めの受診が大事ですね。
杉山:気軽な気持ちで健康診断に行くのは良いことだと思います。
丸山:最近は薬局やスーパーに保健師がいて、健康相談ができる場もありますよね。
杉山:そういう第三者の言葉って、家族の言葉より響くことがありますよね。
丸山:家族だと「黙れ」と思ってしまうこともありますしね(笑)。
杉山:20代の頃は仕事やプライベートのことで頭がいっぱいで、介護について考える余裕がなかったんです。
丸山:20代は恋愛や旅行、色々やりたい時期ですもんね。
杉山:そうなんです。だから家に帰るのがしんどくて、朝まで飲んで仕事に行くこともありました。でも、そういう時に支えてくれたのがケアマネージャーや施設の方々、近所の人たちでした。
丸山:もし当時の自分にアドバイスできるなら?
杉山:すぐにケアマネージャーに不安を全部話すことですね。
丸山:ケアマネージャーとはどう知り合ったんですか?
杉山:祖母の介護の時から知っていたので、信頼関係がありました。
丸山:それは心強いですね。
杉山:介護にはお金の問題もあって、正直な話、家計のことも相談していました。
丸山:施設にもいろんなランクがあるし、選択の連続ですよね。
杉山:そうですね。だからこそ、信頼できる人がいるのが大事です。
丸山:コロナ禍での面会制限は辛かったですよね。
杉山:そうでしたね。施設のスタッフも感染対策で本当に大変でした。
丸山:さて、参加者の方からの質問ですが、一番辛かったことは?
杉山:父が自分を認識しなかったことですね。でも、だんだん慣れて、「今日は友達として接してくれてるんだな」と思えるようになりました。
丸山:その考え方は誰かに教わったんですか?
杉山:自然とそう思うようになりました。でも、心が弱っている時は泣くこともありましたよ。
丸山:介護を通して自分自身とも向き合うことになったんですね。
杉山:そうですね。でも、母がいてくれたので、二人で協力して介護できたのが大きかったです。
丸山:施設に入ると親子の関係が終わったように感じる人もいますが?
杉山:そんなことはないです!むしろ純粋に親子の時間を楽しめるようになりました。
丸山:介護の経験を通して、日常の小さな幸せが宝物に思えるようになったんですね。
杉山:本当にそうです。父と過ごした日々は、かけがえのない時間でした。
丸山:最後に、介護が不安な人にアドバイスをお願いします。
杉山:一人で抱え込まないで、周りの人に頼ることが大事です。介護はチーム戦ですから。