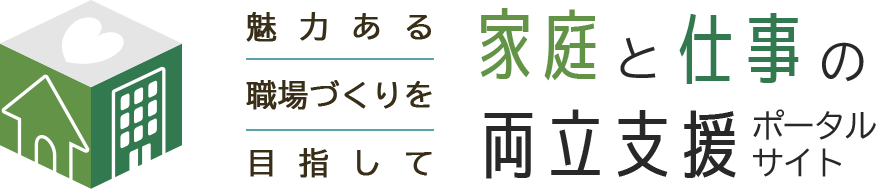事例16:ソフトバンク株式会社
制度の有効活用で仕事と介護とを両立する従業員を継続的に支える
ソフトバンク株式会社
1.企業概要
創業年:1986年
所在地:東京都港区海岸一丁目7番1号
従業員数:18,889人(男性72.9%、女性 27.1%比平均年齢41.3歳)
介護休業取得率 : 1 %未満
事業内容:移動通信サービスの提供、携帯端末の販売、固定通信サービスの提供、インターネット接続サービスの提供
2.取組の背景
「ワークライフバランス」という言葉が世間で広まってきたのと同時に、従業員に仕事で活躍してもらうには家庭の問題を切り離せないという観点から、2007年に、「育児支援」と併せて「介護支援」に関する支援制度を規程で明文化しました。それ以降、「育児や介護」と仕事との両立を会社が積極的に支援するという姿勢を見せることで、従業員には、モチベーションをより一層高く持ち、仕事でも活躍するチャンスをつかんでもらいたい、という理念で支援を継続しました。介護を実際に担う従業員が増えてきた2016~2017年頃から、
①社内の専門部署の設置による制度利用サポート
②実態把握のためのアンケート
③介護ポータルの開設
など、より具体的かつ積極的な施策を実施してきました。 さらに2025年問題を見据えて、もう一歩踏み込んだアプローチをするために、担当役員から従業員へ向けて『介護支援ポリシー』を発信することで、当事者(介護中従業員)および非当事者(介護がまだ始まっていない従業員)両方に「介護」について意識することを促しています。そういった歴史の中で常に根底にあったのは、「介護でキャリアを諦めてほしくない(介護離職はしないでほしい)」「介護があっても支援制度を効率的に活用することで両立を図り、仕事でも活躍してほしい」という想いでした。
3.取組内容
先述のとおり、当社では従業員が仕事と介護を両立させるための支援体制を整え、介護をしながらも仕事で活躍できるよう以下のような取り組みをしています。
【 制度面の整備 】
●介護休業:通算1年間、分割取得の回数制限無し、要介護度「要支援1」の状態から利用可能、2親等以内のすべての親族を対象としており、法定基準を上回った制度としています。また積立年休※を充当することで有給化することが可能です。※「積立年休」:2年間の有効期限が切れた年次有給休暇を積み立て、無給休暇などに充当することで有給化を可能とする制度。
●介護休暇:上記の介護休業と同様の要介護度かつ家族範囲において、対象家族一人に対して10労働日/年度の積立年休充当による有給化が可能で、法定基準を上回る制度です。
●介護のための勤務措置:コアタイムなしの短時間フレックス勤務等、介護を担いながらも日々の業務を行い、活躍に繋げるための環境を整備しています。
このように法定基準を上回る制度を整えながらも、自身が介護そのものに携わるというよりも、あくまでも「家族内の介護体制をマネジメントする(介護体制を整える)」ための制度であるということの理解浸透を図っています。
【 継続的な情報提供 】
「自分もいつかは介護をすることになるだろう」とわかっていても、実際に始まってみないと主体的に情報収集しないものです。当社ではeラーニング等を通して、介護未経験の従業員も「介護の基本知識」を習得し、スムーズな初動のために備えてもらうことを重要視しています。さらに、既に介護が始まっている従業員に対しては①「介護ポータル」「イントラネット」「介護ハンドブック」に情報を集約しいつでもアクセスできる環境を整えていること、②「介護メールマガジン」にてコラムや制度利用案内、社内の介護経験者の体験談等、その時々の旬な情報を発信すること、③介護支援を専門とする外部企業監修の”介護お役立ち情報”ライブラリの提供、④「介護セミナー」を開催し専門家による講義で両立の意義等への理解定着を図ること、などの様々な方向からのアプローチで情報提供を行っています。1回発信したら終わりではなく、常に「新しく介護が始まった従業員」がいることを念頭に置き、継続的に情報発信を行うことが大事だという意識で取り組んでいます。
【 実態把握調査 】
アンケート形式で従業員の介護に関する実態を調査し、介護の有無や困難に感じていること、会社へ希望すること等を定期的に把握し、制度見直し等に役立てています。
【 専門家相談窓口の設置 】
会社の支援制度については社内の担当部署で相談に乗ることができますが、実際の介護についてどういうアクションをしたらよいか、支え合う家族間でどういう協力をしたらよいのか、そもそも介護が始まったばかりで一体どうしたらよいかわからない、といった相談にも対応するため、介護分野の専門家に直接相談できる窓口を設置し、無料で相談できる体制を整えています。
【 柔軟な働き方 】
介護に限ることではありませんが、全社的な動きとしてAIやテクノロジーを活用した業務効率化を図ることで、よりワークライフバランスを取りながらイノベーティブな仕事ができるよう取り組んでいます。また業務の属人化を回避して、いつどこに欠員が生じてもカバーしあえるような体制をとれるよう呼びかけをしています。さらに、組織と個人のパフォーマンスの最大化を目的として、出社と在宅勤務などを効率的に組み合わせた働き方を推進し、介護をはじめとしたプライベートを大切にしながらも、誰もが活躍できる環境を整備しています。
4.これまでの効果と、今後の課題
以上のような取り組みと、法改正等の世間的な後押しもあり、徐々に従業員の「介護」への理解が浸透してきていると感じています。今後の課題としては、当事者/非当事者の両方に対して、継続的な情報発信を行っていくことと併せて、当事者同士が情報交換しコミュニケーションを図れるような場の提供をしていきたいと考えています。 アンケートや介護体験談のインタビュー等から、家族の介護については自分からなかなか話しにくく、従業員が孤立しながら悩みを抱えている現状が見えています。制度面での支援体制は整ってきているので、さらにそれをブラッシュアップしつつ、次なるステップとして、当事者同士が共感し合って心の拠り処にできるような仕掛けも作っていきたいと思っています。
※令和6年11月時点の情報です。