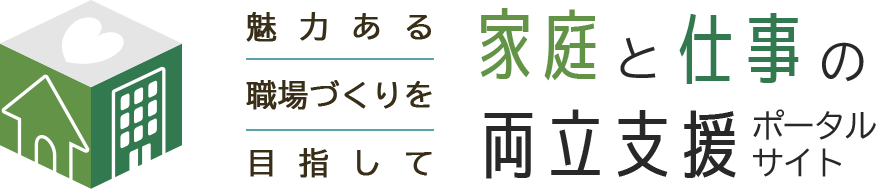事例17:三井住友海上火災保険株式会社
介護の社外相談窓口で従業員に多くの情報を提供する
三井住友海上火災保険株式会社
1.企業概要
設立年:大正7年(1918年)10月21日
所在地:〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9
従業員数:12,093名
事業内容:損害保険業
2.取組の背景
当社では仕事と介護の両立という課題に対して、従来より多角的な支援策を講じてきました。法定を上回る最大365日の取得が可能な「介護休業制度」や、介護休業給付金に会社独自の割合を上乗せして支給する経済的支援は、その一環です。また、個々の事情に応じた柔軟な働き方を実現するためフレックスタイム勤務制度やシフト勤務制度を導入しており、これらの制度は介護を担う従業員も、もちろん利用することができます。
しかし、これらの制度を整備する一方で、従業員が実際にどのような不安や困難を抱えているのか、より深く理解する必要があると感じていました。そこで昨年、介護中の従業員を対象としたヒアリングを実施しました。
このヒアリングを通じて明らかになったのは、多くの従業員が現在進行形で介護に直面している、あるいは将来の介護に対して漠然とした、しかし根深い不安を抱いているという実態でした。当社は日本全国および海外にも拠点があり、転勤や海外赴任を経験する社員が多数となっています。そのため、介護の問題は単なる私生活の課題にとどまらず、従業員のキャリアプランに関係する課題であることが、改めて浮き彫りになりました。また、寄せられた相談内容には要介護者の心身の状態、同居か別居か、近距離か遠距離かといった物理的な状況など、一つとして同じケースはありません。これらの千差万別な悩みに、人事部が画一的な制度だけで対応するには限界があると考えました。
3.取組内容
そこで当社では一人ひとりの従業員が抱える個別の事情に、より専門的な知見をもって寄り添うために、「従業員のための介護個別相談窓口」を設置しました。この窓口では、ケアマネージャーを含む専門家に対し、当社の従業員が直接、電話やメール・WEB面談を通じて気軽に相談することができます。介護が現実のものとなる前の段階から、あるいは介護が始まったばかりで戸惑いの多い時期において、従業員と「介護のプロ」を繋ぐことで、精神的な負担を軽減し、仕事との両立に向けた具体的な道筋を共に探していくことを目的としています。
本相談窓口は当社の全従業員が利用可能です。また、支援の対象となる被介護者についても一切の制限を設けておらず、従業員が「支えたい」と願う大切な方に関する悩みであれば、どのような内容でも専門家に相談することができます。利用方法については、従業員が自身で社内ポータルサイトに設置された専用リンクから外部の相談窓口にアクセスします。人事部への利用申請や上司への報告は不要で、心理的な負担を限りなくゼロに近づけ、思い立ったときにすぐ利用できる仕組みを構築しました。
本相談窓口は当社の全従業員が利用可能です。また、支援の対象となる被介護者についても一切の制限を設けておらず、従業員が「支えたい」と願う大切な方に関する悩みであれば、どのような内容でも専門家に相談することができます。利用方法については、従業員が自身で社内ポータルサイトに設置された専用リンクから外部の相談窓口にアクセスします。人事部への利用申請や上司への報告は不要で、心理的な負担を限りなくゼロに近づけ、思い立ったときにすぐ利用できる仕組みを構築しました。
相談手段としては、電話・メールそしてWeb面談の3つの選択肢を用意しています。中でも当社が特に推奨しているのが、お互いの顔が見えるWeb面談です。文章や声だけでは伝わりきらない相談者の表情や雰囲気から、介護の専門家がその方のストレスや不安の度合いをより深く、正確に感じ取ることができると考えています。本制度は導入からまだ1年未満ということもあり、まずはこのサポート体制があることを全従業員に広く周知し、一人でも多くの社員に「ここに相談すればいい」という安心感を持ってもらうことに注力しています。
4.これまでの効果と、今後の課題
制度の導入から1年未満ではありますが、すでに従業員からは数々の前向きな反響が寄せられており、特に「従業員自身の精神的なケア」という面で大きな手応えを感じています。育児とは異なり、介護はいつまで続くのか、明日どうなるのかという見通しが立てにくく、介護者が精神的に疲弊しやすいという側面があります。専門家が親身に話を聞き、状況を整理してくれるこの相談窓口は、出口の見えない不安を抱える従業員の心の拠り所としても機能しています。また、介護の具体的なノウハウを提供するだけでなく、社員の状況や希望に応じて、全国各地の自治体が設置している地域包括支援センターの紹介や介護保険適用外のサービスなども含めた総合的なアドバイスも行っており、これも大きな安心に繋がっているようです。
最近では、この窓口が「セカンドオピニオン」のような役割を果たし、ご家族の健康状態の改善に繋がった印象的な事例も出てきました。ある海外赴任中の従業員が、一時帰国した際に「要介護2」の認定を受けている親の様子に、これまでとは違う僅かな違和感を覚えました。その漠然とした不安を相談窓口のケアマネージャーに打ち明けたところ、改めて医療機関を受診することを勧められました。その結果、新たに認知症が判明し、より適切な介護方針へと繋げることができました。ご家族だからこそ気づく小さな変化のサインを、専門家が的確に受け止め、具体的なアクションに繋げられたのだと考えています。
一方で社外相談窓口については、「周知の徹底」が今後の課題だと考えています。従業員がいざ介護という現実に直面し、不安や混乱の中にいる時に、この相談窓口の存在をすぐに思い出し、アクセスできるような体制をいかに構築していくかが重要だと認識しています。今後は、単に「このような制度があります」と告知するだけでなく、コミュニティ形成や法改正についての研修などを通じて、従業員一人ひとりの介護に対するリテラシーそのものを向上させていきたいと考えています。
介護を特別なことではなく、誰もがキャリアを諦めることなく乗り越えることができるライフイベントとして捉えられる企業文化を醸成し、真の意味での「介護と仕事の両立」を実現したいと考えています。