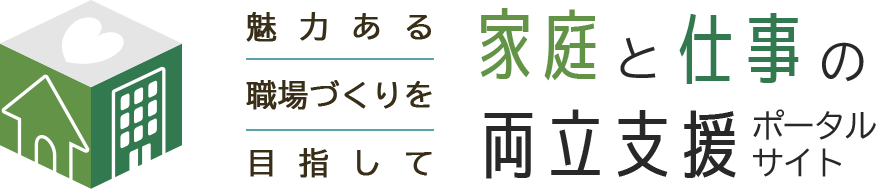- HOME
- 介護と仕事の両立
- 仕事と介護の両立体験談
- 体験談:A.Hさん
体験談:A.Hさん
入社後2週間で始まった介護と仕事の両立
【プロフィール】
●性別・年齢:女性・30代
●勤務先の事業内容:医療・介護の人材紹介事業など
●従業員規模:連結:約4,000人、単体:約3,000人
●職務:事業開発、企画営業
●家族構成:母68歳 要介護1
●居住地:東京都
1.経験した状況
私の母は長年にわたり心疾患、側弯症、骨粗しょう症、そして精神疾患といった複数の持病を抱えており、父が仕事を続けながら母の介護を行う生活が続いていました。私は学生時代に実家を離れていたため当初はこの状況に気づかずに過ごしていましたが、ある時期から母が外出することが難しくなり、そこから数年間は父が一人で母の介護を担う「老老介護」の状態になっていました。そんな中、2年前に父が突然肺がんステージⅣと診断され、余命宣告を受けるという出来事が起こりました。まさか父が病気になるとは思ってもおらず、衝撃と共に深い悲しみと不安を覚えました。私は一人っ子で、介護を共に行う兄弟もいないため、父の治療と介護、そして母の介護を担う必要がありました。私は仕事を続けながら両親2人の介護をどう両立させるかという難題を突きつけられました。
父が亡くなるまでの1年半、私は仕事を続けながら両親の介護を行う日々を送りました。父の体調が悪化する中での介護は身体的にも精神的にも大きな負担がありました。さらに父を看取った後も、母の介護は続いており、現在も自分の住まいと実家を行き来する生活を続けています。
2.どのような介護サービスを利用していますか
介護サービスは、在宅での介護を少しでも円滑に進めるために大変助けになっていると感じます。ただし、介護サービスの利用には家族だけでなく、被介護者自身の意向も大きな影響を及ぼします。私の母の場合、訪問リハビリといったサービスに対して、他人が家に入ることを嫌がる傾向がありました。そのため、こうしたサービスを必要としていても受け入れることが難しい時もあります。訪問介護やデイサービスなどが母にとって有益な選択肢だと感じて見学の予約をしても、母自身が電話してその予約をキャンセルしてしまうこともあり、なかなかスムーズに進まないことも多々あります。
それでも地域包括センターに相談することで、具体的な対応方法や介護保険の申請手続きについてのアドバイスを受けることができています。また、実際に福祉用具の貸与、住宅改修、配食サービスなどを利用する事もできました。
3.ご家族やご親族、その他の方から介護の支援を受けることはありますか。
私には兄弟がおらず、親族も高齢のため、介護は私一人で行っています。この状況では、家族間で役割を分担することができないため、介護と仕事を両立する毎日は体力的にも精神的にも大きな負担を感じることがありました。それでも、近所に住む友人や知人が時折助けてくれることで、何とか日々の生活を乗り越えています。たとえば、私が仕事で忙しい時の通院への付き添いや、不在時の食料品の買い物など、彼らのサポートは本当に大きな支えとなっています。p>
ただし、専門的な支援を受けることにはいくつかの課題があります。特に、ケアマネジャーを通じた介護サービスの利用については、被介護者である母が難色を示しているため、現時点では十分なサポートを受けられていません。母は外部の人が介入することに対して抵抗感を持っており、その気持ちを尊重しながらも、介護の負担を少しでも軽減する方法を模索しています。
4.仕事と介護の両立の悩み
私の介護経験は、現在の職場に転職してわずか2週間後に突然始まりました。父が肺がんのステージⅣと診断され、余命宣告を受けたことがきっかけでした。それまで父が比較的健康な状態であると信じていた私にとって、この知らせは大きな衝撃でした。同時に、転職したばかりの新しい環境で業務を覚えながら、介護の必要性に直面したことで、どう対応すれば良いのか全く分からず、大きな不安と焦りに駆られました。
入社後は前任者との引き継ぎ期間中で、新しい職場でやりたいことも多くありましたが、自分の介護状況が職場や周囲に迷惑をかけるのではないかと心配になり、何度も退職を考えました。そんな中、まずは状況を上司に相談することにしました。まだ入社して間もない私の相談に対して、上司は親身になって話を聞いてくださり、人事労務課にも働き方について相談する機会を設けていただきました。また、地域包括センターに相談することで、両親の状態に応じた具体的な対応方法や介護保険の申請手続きについてのアドバイスを受けることができ、少しずつ介護と仕事の両立のための体制を整えることもできました。
現在の職場では勤務開始時間を柔軟に選択できる制度があり、私は午前7時30分に勤務を開始することで、16時30分に仕事を終えるスケジュールを選ぶ事ができました。これにより、時間休を利用せずとも母の病院受診などのサポートが可能になっています。また、職務上どうしても出社が必要な日もありますが、上司の配慮と職場の介護申請によって、特別にリモート勤務を許可していただけるようになり、実家での介護と仕事の両立が実現しました。
それでも、毎日のスケジュール管理を徹底しています。例えば、事前に食事や買い物の準備をし、不測の事態が起こる前提で仕事のスケジュールを調整しています。社内会議を曜日に集約したり、介護関連の公的機関やサービスが利用できない時間帯に勤務を集中させたりしています。また、自分の状況を職場の同僚に正直に伝えたことで、急な欠席やスケジュール調整にも協力を得られるようになり、介護と仕事の両立が少しずつしやすくなってきました。
今振り返ると、介護と仕事の両立を模索し始めた初期の10カ月間は、先が見えない不安から精神的に落ち込み、睡眠不足や不安に襲われる日々が続きました。その中で気づいたのは、「すべてを完璧にこなそうとしないこと」の大切さです。自分のキャパシティを過大評価せず、できることとできないことを見極めるように意識することで、精神的な負担を軽減し、状況に対応できるようになりました。今では時間の使い方を工夫し、目の前の課題に一つ一つ丁寧に向き合うことで、介護と仕事の両立に向けたペースを少しずつつかみつつあります。
5.仕事と介護の両立のコツ
以前の私は、親の介護について「自分の親なのだから、すべて自分で行わなければならない」と思い込んでいました。しかし、その考えに縛られることで精神的にも肉体的にも追い詰められている自分に気づき、発想を転換することが必要だと感じました。自分でなければならない部分と、他の人やサービスに委ねても良い部分を分けることで、負担を軽減し、気持ちに余裕が持てるようになりました。
たとえば、家事や通院の付き添いなどは、有償のサービスを活用することで、時間的な余裕を作ることができます。また、私にとっては実家の近所に住む同級生や知人の存在が非常に大きな助けとなっています。母は外部の人との接触を苦手とする一方で、旧知の仲である彼らとは安心して関われるため、通院の付き添いや買い物の手伝いをお願いできる状況です。このような繋がりが母にとっても私にとっても心の支えになっています。改めて、地域や人との繋がりの大切さを実感し、こうした友人たちの存在を「人生の財産」と感じるようになりました。
また、私が仕事を続けられているのは、職場の理解とサポートのおかげであると深く感謝しています。急な休暇や早退が必要になることも多々あり、同僚や上司に負担をかけてしまう場面もあります。それでも、職場の誰も嫌な顔をせず、私の事情を尊重してくれています。
6.介護を行っている若い労働者へのアドバイス
私は36歳のときに突然、両親の介護が始まりました。同世代で介護を経験している人は少なく、当初は誰にも相談できず、一人で抱え込む日々を過ごしていました。しかし、思い切って自分の状況を周囲に話してみると、少数ながら親が祖父母の介護をしており、そのサポートに孫である友人や知人も参加していることが分かり、少しずつ孤独感が和らいでいきました。ある日、職場で親の介護をしていることを話したところ、年齢が自分よりも若い部下が「実は自分も介護をしています」と打ち明けてくれることがありました。この経験から、人に話すことで見えてくる共感や支援の可能性を実感しました。
介護はいつ終わるのかという見通しが立ちにくいと感じ、不安や負担感に押しつぶされそうになることも少なくありません。しかし、周囲の人に相談し、話を聞いてもらうことで、心の重荷が軽くなることもあると気づきました。また、自分自身のケアも介護生活を乗り越える上で非常に重要だと感じています。仕事と介護を両立していると、どうしても時間に追われがちですが、リフレッシュする時間を意識的に確保することで、心身のバランスを保つことができます。私の場合、短時間で完結する趣味を持つことで、日常のストレスを定期的に解消するようにしています。
さらに、介護は経済的な負担も大きいものです。介護生活の終わりを迎えた後、自分自身の人生をどのように再構築するかを考える必要があります。私も介護開始当初は仕事を辞めるべきか悩みましたが、離職せずに働き続ける選択をして本当に良かったと思っています。もし離職していたら、経済的な問題がさらに深刻化し、将来への不安も一層大きなものになっていたことでしょう。加えて、仕事をしている時間は、介護のことを一時的に忘れられる貴重な時間でもあります。
私が介護を始めたのは、転職してわずか2カ月後のことでした。当時は悲しみと不安・混乱の連続でしたが、会社の上司や人事労務の方々のサポート、職場の介護支援制度、そして同僚や旧知の友人たちの支えによって、何とか仕事と介護を両立できています。地域包括支援センターや専門家から得たアドバイスを基に、介護保険や民間サービスの活用方法を学び、情報収集を続けていることも、突発的な事態に対応できる助けとなっています。
介護生活は決して平坦ではなく、課題も尽きませんが、私は今後も仕事と介護の両立に取り組み続けたいと思います。他の人々の支えや理解、そして必要なときに相談する勇気があれば、両立の道を切り開けると信じています。この経験を通じて得た学びを活かしながら、前向きに歩んでいきたいです。