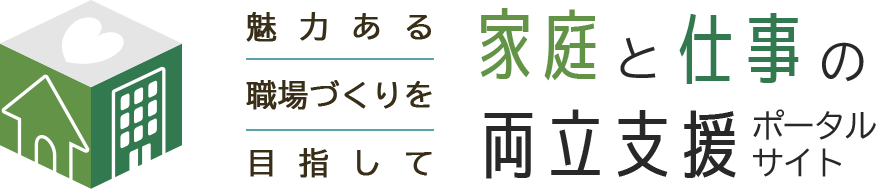育業中のスキルアップは、復職後の育児と仕事の両立を楽にする
コラム
育業中のスキルアップは、復職後の育児と仕事の両立を楽にする
株式会社ワークシフト研究所所長/静岡県立大学経営情報学部准教授
国保 祥子
■育児休業の目的とその課題
育児休業制度は1991年に公布され、1992年4月より施行された育児・介護休業法によって制定されました。これが育休制度のはじまりです。1995年には育児休業給付が創設され、休業中の被保険者に雇用保険から給付金が支払われるようになりました。その後給付率や給付期間を拡充しながら、現在に至ります。男性に関しては、2010年には夫婦での取得を促進するパパ・ママ育休プラス制度が施行され、2023年には男性育休取得者の公表義務が企業に課されたことで取得率が30%を越えるようになりました。
東京都は、育児休業の愛称を育業と定めました。育業は休暇ではなく、育児や介護を行う国民の職業生活と家庭生活との両立のための支援です。近年は転職市場が活発化してきましたが、1990年代は転職がまだまだ一般的ではなく、出産時に退職をせざるをえなかったり、退職すると再就職が難しかったりという問題がありました。しかし育児中の休業が認められたことで、出産後の休業期間を経て就業を継続しやすくなりました。それでも2010年頃までは6割程度が出産を機に離職しており、育児と両立しながら働くことは簡単ではないことが分かります。今では大手企業では育業からの復職率は100%に近くなっていますが、家事育児といった家庭内タスクが女性に集中している状態は変わっておらず、結果として退職に至ったり、比較的責任が軽く両立はしやすいがキャリアアップの可能性が低くなるキャリアトラックである「マミートラック」に陥ったりする女性が多発しています。
公益財団法人21世紀職業財団の26歳~40歳(1980年~1995年生まれ)で配偶者・こどもがいる正社員の女性を対象とした2022年の全国調査※1では、「難易度や責任の度合いが低く、キャリアの展望もない(マミートラックにいる)」と回答した人が46.6%、「難易度や責任の度合いが妊娠・出産前とあまり変わらず、キャリアの展望もある(キャリア展望がある)」と回答した人は40.5%、「難易度や責任の度合いが高すぎて、荷が重い(荷が重い)」と回答した人は12.9%という結果でした。また総合職と一般職で分けて見ると、総合職では「キャリア展望がある」が53.0%、「マミートラック」が39.0%、「荷が重い」が8.0%、一般職では「キャリア展望がある」が37.9%、「マミートラック」が50.6%、「荷が重い」が11.5%という結果となっていました。一般職の5割、総合職でも4割がマミートラックにいるのです。
そもそも育業は、給付金の財源が雇用保険であることからも分かるように、育児をしやすくするための制度というよりは、労働者の雇用の安定や円滑な職場復帰を促進し、就業を継続しやすくするための制度です。しかしいくつかの研究では、育業を取得すること、特に長期間取得することがキャリアにマイナスの影響を与えると言われています。
例えばカナダの研究※2では、取得した産育休が長いことでその女性の主体性(agency)や仕事への熱意が低いと見なされる傾向があり、その結果、実態とは別に仕事へのコミットメントや雇用適性が低い人材なのだと評価されやすいということが明らかになりました。これは、産育休の長さが主体性や労働意欲を測る尺度としても使われているということなので、時短勤務制度を利用している人も労働時間が短いことから意欲が低いと見なされている可能性があります。
ただしこの研究では、育業中に「復職支援プログラムに参加した」という情報があると、これが主体性の証明になるため、主体性が低いという評価にならないということが確認されています。つまり育業中に主体性を発揮したという証拠があることで、人材としての評価が変わるのです。
■育休プチMBA®という社会実験
私は、2014年に育休プチMBAという育業中の人を対象としたビジネススキルアップのための勉強会を立ち上げています。この活動を続けている中で、育業を取って仕事を続けようとしている人たちが復職後の生活に対する不安を抱えていること、その不安ゆえの消極的な言動が客観的には「仕事へのモチベーションが低くなっている」と見なされやすいということが分かってきました。またこの勉強会に参加した人たちが、復職後に高く評価されている事例もたくさん目にしました。
そこでこの現象をアカデミックな観点で捉えるために、2017年度と2018年度に育休プチMBAをベースとした復職支援プログラムを実施しました。プログラムは全4回のワークショップで構成され、ケースメソッド教授法を採用し、参加者の視座を育業からの復職当事者から、その上司、そして他部署や取引先と視座をあげていく(=視点取得)内容になっています。このプログラムを人事部の方から告知いただく形で企業横断的に参加者を集め、その参加者を対象にワークショップの参加前、参加直後、育業復帰前、育業から復帰して半年という4つのタイミングで意識調査を実施しました。復帰後の調査はご本人に加えて上司にもアンケートを実施しています。同時に、このワークショップに参加しなかった育業者にもアンケート調査を実施し、参加者と非参加者の間にどういった違いがあるのかということも調査しました。
その結果、まずプログラムを受講することによって復帰後の家族と仕事の干渉への懸念(復職後の生活への不安)が有意に減少する一方で、仕事と家庭を両立できそうだという自信(両立効力感)と、管理職になってもやっていけそうだという自信(管理職効力感)が有意に増加していることが確認できました。つまりプログラムを受講することによって、両立後の不安が減り、自分は復職後もうまくやっていけそうだという自信と、管理職になってもうまくやっていけそうだという自信が高まったということが確認できました。
また復職半年後の調査によって、復職後の生活への不安の減少が実際にどう影響するのかを調査しました。すると研修によって両立効力感を高めた人たちは、上司から見て評価してもチームのメンバーとして優れた役割を果たしてくれている(役割遂行パフォーマンスが高い)ということが分かりました。両立効力感を高めた人たちは、本人が自分の仕事をしっかりこなしているだけではなく、チームを意識して動けている、それが上司に評価されているのです。復職前の自信を高めることが、復職後の活躍につながると言えます。
一方で、プログラムに参加しない人はどうだったのか。このプログラムへの参加者と非参加者の受講前の状態、すなわち初期値はほとんど変わりません。どちらも同じぐらい不安を抱えている状態です。しかしプログラムへの参加者が受講を通じて不安を減少させているのに対して、非参加者は復職前にさらに不安を強めています。同時に両立効力感についても、非参加者の方は復職直前には更に下げているという状態でした。復職支援プログラムに参加しないと、高い不安状態で復職を迎えてしまうということです。なおプログラム参加者と比べると、非参加者は家族の支援が少ないという傾向がありました。家族の支援が両立の不安に繋がっていると考えられます。
実際にワークショップを実施している間も、育業者の高い不安は感じました。不安の理由のひとつは、「復職後は会社から期待されなくなる」という予測で、残業やイレギュラー対応ができない不完全なメンバーとして組織に戻る罪悪感が大きいのです。会社側が行う配慮や遠慮も、遠慮というより「もう期待されなくなったんだ」という捉え方をする人が多くいました。そして期待されていない不十分なメンバーだという自覚があることで、キャリアに対する要望や意気込みを口にできなくなる、ということが分かりました。しかし「会社は皆さんの今後の活躍に期待をしていますよ」ということを伝えると、面白いことに急に課題解決思考になるのです。具体的には、例えば、期待されていないという捉え方をしている時は「いかに迷惑にならないようにするか」という思考になってしまっていても、期待されていると感じると、「自分の抱える制約の中で期待に応えるにはどうすればよいか」を考えるようになっていきます。
■両立しながら働く人の「ライフゲージ」を管理する
この現象は、資源保存論という理論で説明できます。資源保存論とは、個人的な資源を獲得保持・保護しようとしたり、資源を失うことによってストレスを感じたりするという理論です。分かりやすい例えとしては、ロールプレイングゲームやバトルゲームのHPやMP、ライフゲージや体力ゲージというものを想像していただくといいかと思います。人はそれぞれライフゲージという資源を持っていて、その資源が減ってしまうと、攻撃に出ることができなくなります。一方でライフゲージが豊富だと、積極的に攻撃しようという気持ちになります。そのためこのライフゲージを適切な量に保っておくということが重要ですが、復職後の両立生活を考えた時に、「今のライフゲージでは難しいのではないか」と感じると、復職者としては不安になり、その不安な状態では「自分のライフゲージをもうこれ以上減らさないようにしよう、最低限のことだけやるようにしよう」と守りに入ってしまうのだと思います。
一方で、今回の復職支援プログラムへ参加した人は、受講を通じて両立効力感を高めることができています。ライフゲージが豊富な状態で復職することができているので、自分の仕事を越えたチームへの貢献行動のような攻めの行動もできており、それ故にチームのメンバーからのサポートというライフゲージの補充に繋がっていることが考えられます。要はこの自分の資源、ライフゲージをいかに高い状態にして復職してもらうことが重要だということが分かりました。
■両立の大変さは個人の意識の影響も大きい
育児と仕事の両立の捉え方に関しては、様々な研究があります。有名なのはワーク・ファミリー・コンフリクトという役割間葛藤(ふたつの役割を果たすには時間が足りないという葛藤)ですが、ひとつの役割がもうひとつの役割の質を向上するというエンリッチメントという考え方もあります。物理的な資源だけではなく、スキルや視点などの心理的な資源、つまりその人の意識の持ち方次第で、両立しているからこそ得られる充実感があるということです。
育業者に限らず、介護や病気治療などで仕事にフルコミットできない人材というのは今後も増えていくでしょう。今後はフルコミットを前提とした職場では人材確保に苦労することが目に見えています。会社が制度を整えたり、支援的な組織風土を作ったりすることは大前提ですが、両立生活が個人の意識の持ち方次第で辛くもなるし楽しくもなりえるのであれば、個人の意識への働きかけも効果的であるといえます。意識変革につながるスキルアップを育業中に行うことは、結果として復職後の育児と仕事の両立を楽にするのです。
※1 子どものいるミレニアル世代夫婦のキャリア意識に関する調査研究(2022年)
https://www.jiwe.or.jp/research-report/2022
※2 Hideg, I., Krstic, A., Trau, R. N. C., & Zarina, T. (2018). The unintended consequences of maternity leaves: How agency interventions mitigate the negative effects of longer legislated maternity leaves. Journal of Applied Psychology, 103(10), 1155–1164.