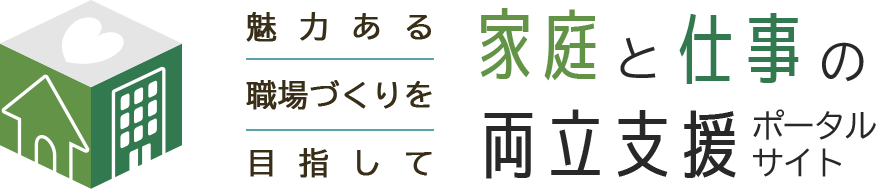- HOME
- 病気治療・不妊治療と仕事の両立
- 不妊治療と仕事の両立 取組事例・両立体験談
- 事例8:株式会社アイエスエフネット
事例8:株式会社アイエスエフネット
不妊治療を計画している従業員、不妊治療中の従業員双方の仕事の両立をワークライフバランス相談窓口によって支援する
1.企業概要
設立年 :2000年
所在地 :東京都港区赤坂7-1-16 オーク赤坂ビル 3F
従業員数 :2,520名(男女比 73:27 平均年齢34.5歳)
事業内容 :情報通信システムの設計、施工、保守及びコンサルタント業務
2.取組の背景
当社は創業当初から各人の背景に関わりなく、人間性を重視して採用を行ってきました。また2016年1月頃から当社の代表の思いを反映し、不妊治療を行っている人についてもふるいにかけず 採用してきました。そのような過程で不妊治療はそこに係る時間と労力、経済上の負担からゴールのない道のりのように感じる方が多いということもよく理解できました。就業した後にも不妊治療を継続する意向を持ち、仕事の両立を希望する従業員がいるため、会社として支援の取組を開始いたしました。2016年には女性従業員の課題に対応するチームが、2021年には女性活躍推進委員会が社内に設立され、女性特有の体調や病気を抱えながら仕事との両立をする従業員をどのように支援していくのか検討しています。当社は女性が妊娠、出産というライフイベントでキャリアを諦めることなく働ける環境を構築したいと願っています。
3.取組内容
当社では不妊治療の他にも性別適合手術やホルモン治療を行う際に、性別に関係なく取得可能な休暇としてセルフケア休暇を取り決めています。従業員がセルフケア休暇を取得するときには、社内で「ダイバーシティ」と「インクルージョン」を掛け合わせて命名した「ダイバーイン推進課」に申請をすることができます。不妊治療を受ける場合には治療の実績を報告すれば、セルフケア休暇として受理されます。さらに社内にはワークライフバランス相談窓口も設置されており、職場の上長を介さずとも不妊治療について相談したり、セルフケア休暇の申請をしたりすることも可能です。セルフケア休暇の日数に関しては、不妊治療を目的としたものは有給で月に1日取得可能です。それ以上の日数の休暇を不妊治療のために取得したい場合は相談も可能です。
職場の多様性を実現すべく、ダイバーイン推進課は設置され活動をしています。当事者の個人情報保護が必要と感じることの多い不妊治療に関しては、従業員がワークライフバランス相談窓口に直接相談することができます。2023年に不妊治療と仕事との両立に関する社長メッセージを発信し、両立支援担当者を任命したことで、ワークライフバランス相談窓口の対応件数が前年比169%を記録するまでに増加しています。
以前は上長に相談してから不妊治療の支援を行うという仕組みでした。しかし不妊治療に関するプライバシーの保護や従業員の気持ちにも着目し、社内で担当部署と人事課中心で進めることにフローを統一しました。そうすることで担当部署が不妊治療を行う本人の許可をまず得てから、上長に報告することを徹底する仕組みを作ることができ、より従業員が不妊治療と仕事を両立しやすくなったと自負しています。
また、ワークライフバランス相談窓口は調整役として重要な役割を担っています。当社の従業員の約9割は客先に常駐していますが、常駐先でも不妊治療のためにセルフケア休暇を申請することができます。その場合には、常駐先にも休暇を報告しなければなりませんが、当社のワークライフバランス相談窓口が従業員に代わって、担当営業と連携し常駐先へ休暇の調整を行うことになっています。そうすることで本人が不妊治療を行っていることを客先に報告する必要もなくなり、心理的な負担が少ない方法でセルフケア休暇を申請することができます。さらに当社もニュースリリースとして社員一人ひとりの働きやすさを追求するために「不妊治療と仕事の両立について」のトップメッセージを積極的に発信することで、顧客の皆さまが当社は従業員の不妊治療支援を行っていることについて、理解していただけるように努力しています。
様々な取組を行いながら、社内に相談窓口があることをより周知するために、女性活躍推進委員会からの情報発信や、社内向け動画を作成するなどの活動を行っています。当社の女性活躍推進委員会のメンバーには男性もおり、ダイバーイン推進課だけではなく、様々な課からの意見を聞き施策を策定しています。そうすることで従業員の男性にも、女性の抱えている悩みを自分事として捉えることができるようになってきたなど、社内の男性従業員の意識が変化してきたと感じています。また社内のハラスメント防止規定の中に他の従業員の病歴、不妊治療の有無などの情報を無理やり聞き出さないという項目も加えることによって、不妊治療を行っている従業員のプライバシー保護に努めています。
4.これまでの効果と、今後の課題
様々な制度の取り決めや、相談窓口を設けましたが2021年には不妊治療を行うことを報告した従業員は非常に少数でした。しかし2023年には2021年の4倍の数の従業員が不妊治療のためにセルフケア休暇を利用し、2024年1月から6月には2023年の1年で利用する数と同等の数の従業員の利用が確認されています。実際にセルフケア休暇を利用した従業員からは、その会社の制度に関して好評を得ています。当社では毎年ワークライフバランスアンケートを従業員に対して行っていますが、今後も継続し、従業員の必要を細かく感じ取っていきたいと目標を定めています。
もし従業員が不妊治療を始めたとして、まだ心配事があるならば引き続きワークライフバランス相談窓口で相談することが可能です。しかし会社の制度だけではなく、不妊治療を行っている従業員に対する他の従業員の気遣いや配慮も必要だと感じています。当社の従業員には障がい者や外国人、LGBTQIAなどの多様性が満ちている中で、不妊治療を行っている従業員に対する配慮が促進されています。また、人間性を重視した雇用を行うことで、細かな規則を強制するよりも互いに対する敬意を重んじる社風が醸成されています。現在では多様性が奇異なものではなく通常のことであるように従業員が認識できるようになっています。
当社としてはセルフケア休暇のさらなる利用を従業員に進めたいと感じています。これからはさらに簡潔にセルフケア休暇を申請できるようにすること、制度に関する社内広報を積極的に行うことで従業員にとってより身近な制度にし、不妊治療に臨もうとする従業員、不妊治療を既に行っている従業員が気持ちよく仕事との両立ができるよう支援を継続していきたいと考えています。