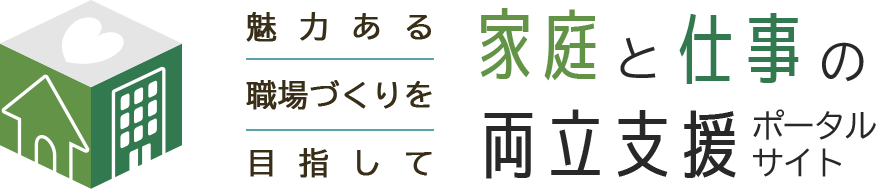- HOME
- 病気治療・不妊治療と仕事の両立
- 病気治療と仕事の両立 取組事例・両立体験談
- 体験談8:M.Kさん
体験談8:M.Kさん
一人で悩むのではなく家族、同僚に相談しながら、社内制度を利用し体調管理と仕事を両立する
【プロフィール】
性別・年齢:女性・30代
勤務先の事業内容:クラウドサービスの開発、販売
従業員規模:約250名
職務:プロダクトマネージャー
家族構成:配偶者
居住地:東京都
1.経験した症状、状況
20代前半から、PMS(月経前症候群)の症状が悪化し、頭痛、腹痛、めまいといった症状に悩まされています。そのため定期的に産婦人科を受診していますが、検査をしても症状に直結する原因は特定できず、対症療法によるケアにとどまっています。普段の業務はデスクワークが中心であるため、医師からは血行の改善をすすめられ、日々の生活にエクササイズを取り入れるよう意識し、長時間座りっぱなしにならないよう上下昇降式のスタンディングデスクを導入してこまめに立ち上がるなど、姿勢にも気を配っています。
PMSの症状の中でも特に「めまい」は大きな悩みの種です。頭痛や腹痛に関しては鎮痛剤である程度対処が可能ですが、めまいに関しては症状を抑えるのが難しく、通勤時間にはさらに大きな負担を感じることが多いです。例えば、めまいがひどい日には、満員電車で通勤するのが特に苦痛で、職場のある駅に到着するまでに何度か途中下車して休憩し、症状が落ち着くのを待たなければならないこともあります。そのため、PMSの無いときと比べると、通勤時間が倍以上かかることも少なくありません。職場に着いた後も、めまいと格闘しながらの仕事を続けるのは非常に辛いものです。特に以前の職場では、PMSに対処するための休みは有給休暇を利用するしかなく、症状が重くなる可能性が高い日を予測して有給を取得する必要がありました。しかし、実際には予想した日に症状が軽かったり、別の日に症状が重くなったりすることが多く、予定通りに休暇を取れない場合もありました。そのため、計画的な休暇取得が難しいばかりか、予測と異なる症状の変動に日々対応しなければならず大きなストレスでした。
2.勤務先の支援体制、利用状況
そのような症状を抱えながらも私は転職の機会を得て、現在の職場で働いています。新しい職場では、オフィス勤務とリモートワークを組み合わせた「ハイブリッドワーク」が推奨されており、特にプロダクトチーム内で事前に調整が取れていれば、積極的にリモートワークを行うことが認められています。PMSの症状が出ているときにはリモートワークを利用することで、辛い通勤を避けることができるのは大きな助けとなっています。また、リモートワークの日には服装もある程度自由に選ぶことができ、体調に合わせてリラックスした環境で仕事ができるため、負担が少なくなりました。さらに、現在の職場では時短勤務も柔軟に利用できるため、PMSの症状がひどい日でも仕事の負担を軽減することが可能です。これにより、自分の体調に合わせて働くことができるため、無理なく仕事を続けられる環境が整っています。このような制度があることは、PMSに悩む私にとって非常にありがたいことであり、働きやすい職場だと感じています。
また、生理時にも使える特別休暇制度が設けられており、この制度を積極的に活用しています。この特別休暇制度は生理(PMS・月経)に伴う体調不良および治療するための通院の他にも、不妊治療や婦人科通院にも使えます。また、女性だけでなく、男性も不妊治療などの目的で利用でき、午前のみ・午後のみといった半日の取得も可能です。これにより、症状が重くなる日に合わせて休むことができるようになり、PMSの症状が出やすい日にピンポイントで休暇を取ることができる点は大変助かっています。
以前の職場では、PMSに対処するために定期的に有給休暇を取得していましたが、その度に他の同僚への遠慮や、自分の勤務態度がどのように評価されているかが気になりましたし、休暇を取得するたびに、自分がチームに迷惑をかけているのではないかと、精神的な負担を感じていました。しかし、現在の職場では、生理のための特別な有給休暇が定められており、半日単位で利用できるため、周囲のメンバーへの負担も減らすことができ、精神的な安心感を得られています。生理やPMSに対する理解が深い職場に転職できたことで、心身の負担が軽減され、働く意欲も向上しました。
3.協力者との関係
職場では、男性を含めた同僚たちがPMSに対して理解を示してくれている、という雰囲気を感じることができています。PMSについては、たとえ女性同士でも症状が異なるため、具体的に詳細を説明して理解してもらうのは難しい面があります。しかし、同僚たちは私が特別休暇制度を取得する際にも踏み込んだ質問をしてくることなく、あえて私に症状の説明を求めることもありません。PMSで体調が辛い時には、このように「わかってくれている感」を醸し出してくれる同僚の存在が心の支えになっており、仕事への取り組みにも安心感が生まれています。
また、社内でこの特別休暇制度が導入される際には、説明会が開催され、人事担当の方が「人によって症状が違います」と強調してくれました。これは、各従業員の健康状態が異なり、それぞれの体調に応じた配慮が必要であるという考え方を広めるもので、PMSに苦しむ当事者である私にとっても、大きな励みとなりました。会社全体で症状に対する理解が進むことで、休暇を取得することへの心理的負担が軽減され、自分らしく働ける環境が整いつつあると感じています。
家庭でも、夫が週に2日リモートワークを行っているため、私のPMSの症状が重いときには、彼が「何かできることある?」と優しい言葉をかけてくれることが多く、家事にも積極的に協力してくれます。このようなパートナーの支えは、体調が悪いときの大きな助けとなっており、家庭内でも無理をせずに過ごすことができるため、精神的にも安心できます。
4.両立のコツ
現在の職場も、初めから女性の健康に関する制度が整っていたわけではありません。むしろ男性従業員が多い職場であったため、PMSなど女性特有の体調不良について理解してもらえるか不安に感じていました。そんな中、人事担当の方が積極的に声をかけてくださり、私の体調について上手にヒアリングをしてくれたのです。どのような症状が出るのか、どのタイミングで辛さを感じるのかといった具体的な点について、丁寧に質問しながら聞き取ってくれました。
その結果、私のようなPMSの症状に悩む社員に配慮した制度が新たに取り決められ、職場全体に少しずつ変化が生まれました。たとえば特別休暇制度やリモートワークの柔軟な利用が認められるようになり、これらの制度が導入されたことで、体調に合わせた働き方がしやすくなりました。このように、職場に話しやすい人がいて、安心して相談できる環境が整っていたことは、私にとって大きな救いとなりました。
自分の体調について理解しようとしてくれる人に話を聞いてもらうことは、体調不良を抱えながら仕事と両立するための重要な支えです。相談できる環境があることで、職場での孤立感や不安が軽減され、無理なく自分らしく働くことができるようになります。
5.両立の悩み
以前の職場では、PMSについて他の同僚にどのように説明すればよいのか悩むことが多く、社内の休憩スペースを頻繁に利用しても良いものか、人目を気にしてしまう場面が少なくありませんでした。特に、めまいがひどい日には通勤途中で休憩を余儀なくされ、遅刻してしまうのではないかと不安になりました。そのたびに、自分の勤務態度がどのように評価されるのかと考えると、職場に着く前から心が重くなり、それがさらにストレスとなって体調に影響を及ぼしていたと思います。このような心配が重なり、体調不良と仕事の両立が一層難しくなっていました。
また、同性の同僚であっても、PMSについて十分に理解してもらえず、意図せず傷つくような言葉をかけられた経験もあります。PMSは個人差が大きく、症状も人それぞれであるため、一律の理解を得ることが難しいと感じる場面も多かったです。このように、仕事内容そのものよりも、職場の環境が体調不良と仕事の両立に与える影響は大きいと実感しています。
6.病気治療をする労働者へのアドバイス
自分の体調や状況について「無理に他の人と共有しない」という心構えは、PMSなど体調不良を抱えて働く上で大切なことだと思います。すべての人に理解を求めるよりも、自分の症状について理解してくれる人を職場で見つける方が、精神的な負担が少なく済むと感じます。もし直属の上司が症状を理解しにくい場合には、人事課の社員や同性の先輩社員に相談し、サポートを得ることが有効です。こうした理解者がいると、体調不良を抱えながらも仕事を両立するためのモチベーションを維持しやすくなります。
また、「無理をしない」ことも大切です。女性特有の体調不良については、周囲に理解されにくいことも多く、つい我慢して働き続けてしまうこともあるかもしれません。しかし、自分の体調に合わせて社内の制度を利用し、無理せずに休暇を取ることで、心身ともに楽になることができます。実際、私自身も以前は社内の休暇制度についてよく理解していない時期があり、必要なサポートを十分に活用できていなかったことがありました。もしかすると、すでに社内に女性特有の体調不良に対応する制度がある場合もあるので、ぜひ一度、自分の職場の制度を調べてみることをお勧めします。一人で悩まず、家族や相談できる同僚に支えられたり、社内制度をうまく活用したりすることで、女性特有の体調不良があっても仕事との両立を続けていきたいと思います。職場や家庭での理解と支援を得ながら、自分に合った働き方を見つけ、無理のない形でキャリアを築いていくことを目指しています。