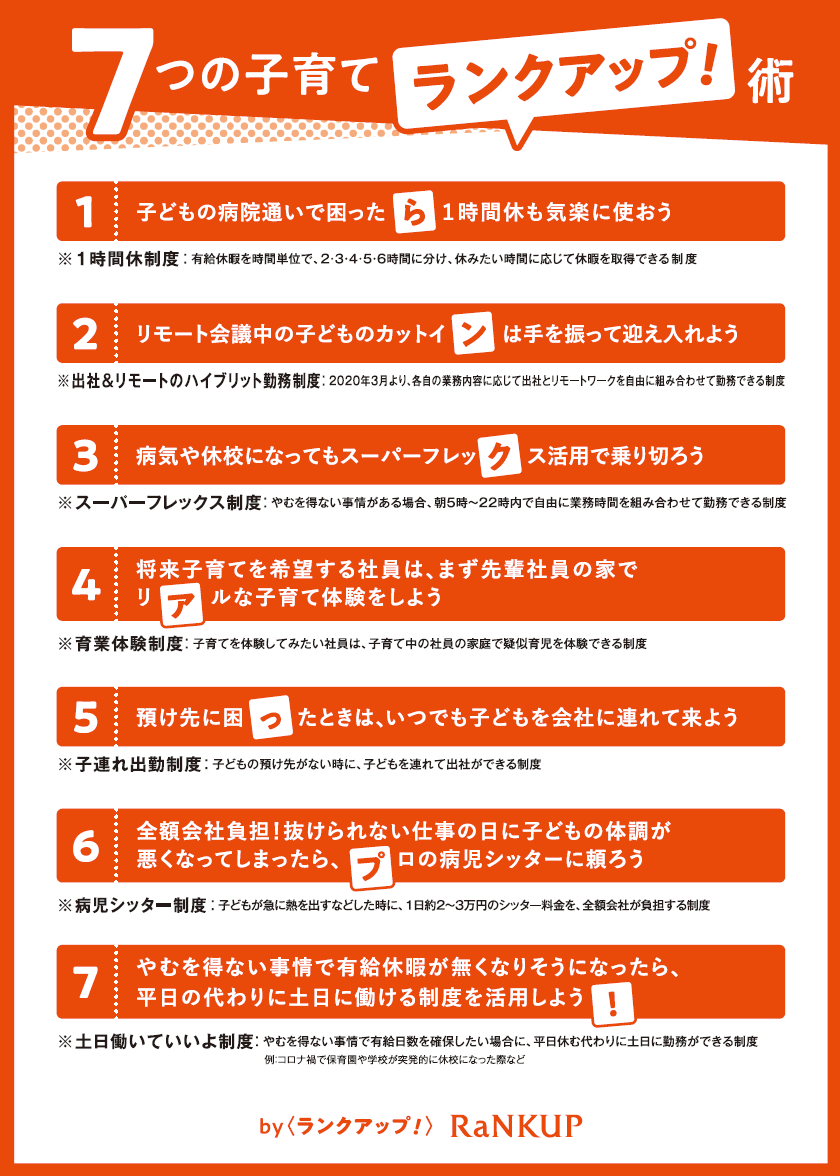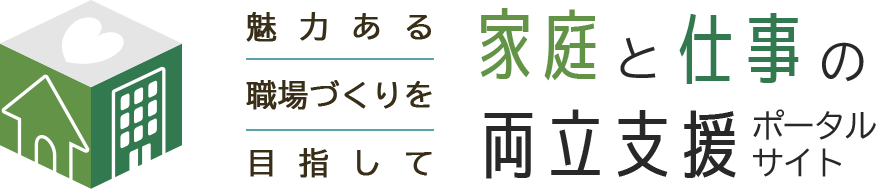- HOME
- 育児と仕事の両立
- 取組事例・両立体験談
- 事例19:株式会社ランクアップ
事例19:株式会社ランクアップ
「男女ともに輝き続ける」を本気で目指す育児と仕事の両立支援
~「育児体験制度」や「子連れ出社制度」の導入・活用~
1.企業概要
設立年 :2005年6月10日
所在地 :〒104-0061 東京都中央区銀座3-10-7 ヒューリック銀座三丁目ビル 7階
従業員数 :105名(2024年10月時点
事業内容 :オリジナルブランド化粧品の開発および販売
2.取組の背景
株式会社ランクアップの数々のユニークな両立支援制度は、創業者の実体験から生まれています。広告業界の第一線でキャリアを重ね、営業本部長として活躍していた創業者は、仕事への情熱とやりがいを感じる一方で、業界に根強く残る「出産するとキャリアの継続は困難」という現実に、自身の未来を重ねていました。「このまま仕事を続けて、家庭を持つことはできるのだろうか。もし持てたとして、仕事との両立は可能なのか。」 その切実な不安について当時はまだ、個人のキャリアとライフイベントを両立させるための制度も、相談に応じる風土もありませんでした。この経験こそが、「社員が結婚や出産といったライフイベントによってキャリアを諦めることなく、一生涯活躍できる会社を創りたい」という強い決意となり、ランクアップ設立の礎となりました。
その想いは、単なる理念に留まらず、明確な経営戦略として制度に落とし込まれています。特に、企業の成長を牽引するエース級の社員が出産を機に離職することは、事業の継続性を揺るがしかねない重大なリスクです。だからこそ、当社は創業以来、「活躍したい人が仕事を継続できる」ための仕組みづくりにこだわってきました。その代表例が、1日2〜3万円にもなる病児シッターの費用を会社が全額負担する「病児シッター使い放題制度」です。これは、子どもの急な発熱による突発的な欠勤をなくし、働く親の精神的・経済的負担と、周囲のメンバーが代わりにしなければならなくなる業務負担を同時に軽減します。また、保育園の休園、夏休みなどの長期休暇の際には、子どもをオフィスに同伴出社できる「子連れ出社制度」も常設。子どもたちの存在が日常の風景となることで、周囲の社員がごく自然にサポートする文化が育まれています。さらに、「長時間労働廃止」や1時間単位の有給取得、柔軟な時短・時差出勤制度を組み合わせることで、社員が学校行事や通院など、日々の細やかな育児の用事に対応しやすい環境を整えました。
これらの充実した制度は、トップダウンではなく、すべて社員の声から生まれています。当社には、社員が自由にアイデアを提案できる「提案制度」という仕組みがあります。当初はなかなか提案が集まりませんでしたが、報酬制度を設けて活性化を図った結果、今では報酬がなくとも社員が自社の課題を自分事として捉え、改善案を出し合う文化が完全に定着しました。すべての提案に対して、経営層が必ずフィードバックを行う真摯な姿勢が、社員のモチベーションを支えています。
そして、この土壌から生まれたのが「育児体験制度」です。特に知っていただきたいのが、この制度が、「子育て中の社員が、周囲に大変さをわかってほしい」という声からではなく、「仕事と育児の両立が、どれほど大変なのかを具体的に知りたい」という、若手社員の純粋な探求心から提案されたことでした。「なぜ、育児中の先輩たちは簡単なチャットの返信すらままならない時間帯があるのだろう?」。その素朴な疑問の裏には、先輩を気遣い、より深く理解したいという温かい想いがありました。育児中の社員のプライベートに立ち入るという、非常にデリケートで実現のハードルが高い提案でしたが、その動機の真摯さに心を動かされ、当社はこの前例のない制度の実現に向けて、真剣に検討することにしました。
3.取組内容
株式会社ランクアップの両立支援制度は、いずれも「利用しやすさ」と「社員への深い信頼」を土台に設計されているのが大きな特徴です。例えば、「病児シッター使い放題制度」は、その名の通り、利用日数や時間に一切の上限がありません。子どもが病気になった際、社員は必要なだけベビーシッターを依頼することができ、その費用はすべて会社が負担します。過去には月に10日間程度利用した社員もいますが、会社側が「使いすぎではないか」といった声かけ等による心理的負担などは一切なく、社員の判断を全面的に尊重しています。また、「子連れ出社制度」も、事前の煩雑な申請や承認は不要です。社内のチャットで「今日、子どもを連れて行きます」と一本連絡を入れるだけで、誰でも気軽に利用できます。特に夏休みなどの長期休暇中は利用者が増え、オフィスが子どもたちの活気で賑わう光景は、当社の日常の一部となっています。
これらの制度がもたらす効果は、単に育児中の社員をサポートするだけに留まりません。「子連れ出社制度」では、子どもたちがオフィスにいるタイミングを見計らい、広報部が主導してクリスマスリユース会や書き初め大会といったイベントを企画しています。これにより、親は安心して業務に集中でき、子どもたちにとっても「お父さんお母さんの会社は楽しい場所」というポジティブな記憶が育まれます。親は長期休暇中の預け先を探すストレスから解放され、子どもは親の働く姿を間近に見たり、他の社員の子どもと友情を育んだりと、家族ぐるみの豊かなコミュニケーションが生まれています。
そして「育児体験制度」もまた、希望する社員なら誰でも参加できる、開かれた制度です。体験希望者は、育児中の社員の退社時間にオフィスを出て、保育園へのお迎えから買い物、夕食の準備、食事、後片付け、子どもとの遊び、お風呂、そして寝かしつけまで、息つく暇もない夜の一連の流れに同行します。この制度の核心は、単なる「見学」ではなく、受け入れ側の親が見守る中で、すべてのタスクを実際に「体験」する点にあります。体験後のレポート提出なども一切不要で、参加者が純粋に学び、感じることを最も大切にしています。
「育児体験制度」がもたらす影響は、さらに深く、個人の意識変革にまで及んでいます。参加者の中でも特に目立つのが男性社員の多さです。ある男性社員はパートナーの妊娠を機にこの制度を利用しました。当初は、周囲の男性社員に倣って2週間から1ヶ月程度の育業を考えていたと言います。しかし、実際に夕方から寝かしつけまでの一連の流れを体験し、「育児とは、これほどまでに膨大で終わりなきタスクの連続なのか」と衝撃を受けました。この体験の影響もあり、最終的に3か月の育業を決意しました。
4.これまでの効果と、今後の課題
「育児体験制度」は、参加した社員に極めて大きなインパクトを与える一方で、その成功が、受け入れ側となる育児中社員とそのご家族の深い理解と協力の上に成り立っているという、デリケートな側面も持ち合わせています。同僚を自宅に招き入れ、キッチンやバスルームといったプライベートな空間まで見せることは、決して簡単なことではありません。この制度が今日も継続できているのは、主旨に賛同し、多大な貢献をしてくださる社員と、そのパートナーをはじめとするご家族の皆様の存在があってこそであり、そのご協力には感謝の言葉しかありません。一度の体験が、人の価値観を大きく変える力を持つ。私たちはこの制度の重要性を深く認識しており、今後もこの「善意の輪」を大切に育んでいきたいと考えています。
そのため、この制度の根幹自体に大きな変更は加えていませんが、より多くの社員が育児に触れる「きっかけ」を作れないかと考え、新たな試みを始めています。それが、オフィスで実施する「プチ育児体験」です。これは、当社の「子連れ出社制度」という土壌があってこそ実現可能な取り組みです。例えば、新入社員の入社式や社内イベントの際に、産休・育休中の社員に赤ちゃんと一緒に来てもらい、新入社員が絵本の読み聞かせを体験するといった機会を設けています。子どもを連れてオフィスに来ることに誰も抵抗を感じない当社の文化が、こうした自然な交流を可能にしています。
本稿で紹介した一連の制度は、「子育て中の社員の大変さを一方的にわかってほしい」という目的で始まったものでは決してありません。私たちの真の願いは、育児の当事者である社員も、これから経験するかもしれない社員も、すべての従業員が互いの背景や価値観を知り、リスペクトし合う文化を創り上げることです。相手の状況を想像し、理解することで、そこにはより強固な協力体制が生まれます。
当社の経営目標は「男女ともに輝き続ける」ことです。社員が会社の制度を主体的に活用し、キャリアを中断することなく、また、性別に関わらず、誰もが自分らしく輝き続けられる人生を歩んでくれること。それこそが、会社として最高の栄誉であり、私たちの目指す未来そのものと考えています。