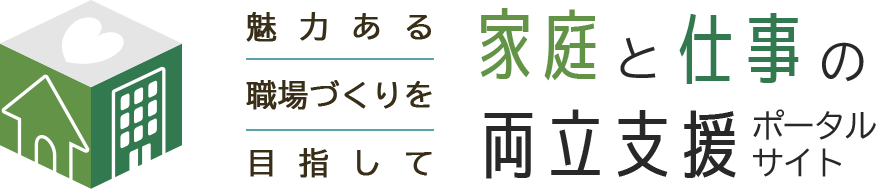- HOME
- 育児と仕事の両立
- 取組事例・両立体験談
- 事例20:全日本空輸株式会社(ANA)
事例20:全日本空輸株式会社(ANA)
社内サポーターによる育児支援「チャイルドケアステーション」の挑戦
1.企業概要
設立年 :2012年4月2日
所在地 :〒105-7140 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
従業員数 :13,636名
事業内容 :定期航空運送事業、不定期航空運送事業、航空機使用事業、その他附帯事業
2.取組の背景
ANAグループは男性社員の育児休業・休暇取得を積極的に促進しています。グループ全体で3日間の「出産・育児に関する特別有給休暇」を取得できる制度を設け、「対象者100%取得」という高い目標を掲げています。目標達成のために重要なのは、制度の存在だけでなく、職場の理解です。本人と上司による1on1ミーティングをきめ細かく実施し、個々の事情やキャリアプランについて対話する機会を設けることで、「休むことへの心理的ハードル」を取り除き、チーム全体でサポートする風土を育んでいます。こうした地道な取り組みの結果、2024年度の男性育児休業取得率は81.5%、休暇を含めたいずれかの取得率は98.6%と、着実に向上しています。
こうした風土づくりと並行して、社員がライフステージの変化にしなやかに対応できるよう、多様で柔軟な働き方の選択肢も提供しています。コアタイムを設けないフレックスタイム制度やリモートワークはもちろん、配偶者の転勤やUターンといった事情に応じてグループ内で転籍できる「ワークプレイス選択制度」や、事由を問わずキャリアを一時中断できる「サバティカル休暇制度」など、ユニークな制度も導入しました。特に、育児休業がキャリアアップの足かせにならないよう、休業期間中の評価を、休業前後の実績から「見なし評価」として適用することで、復職後すぐに管理職試験に挑戦することを可能にしました。これにより、短時間勤務で管理職として活躍する社員も増加しています。同時に、「育児中は大変だろうから」といった管理職の「行き過ぎた配慮」が本人の成長機会を奪ったり意欲を削いでしまったりすることのないよう、管理職向けの研修を定期的に開催し、育児をしながらキャリアを追求したいと願う社員の想いに、組織として真摯に向き合っています。
このような手厚い両立支援制度を整える中でも、客室乗務員のように宿泊を伴ったり、深夜早朝などの航空業界特有の勤務形態による課題は存在しました。その課題に光を当て、新たな解決策を生み出したのが、社員発案による保育サービス「チャイルドケアステーション(CCS)」です。このアイデアは、ANAグループの新規事業提案制度「Da Vinci Camp」から生まれました。発案者である社員は、育児中の同僚が急な勤務変更で東京-ロンドン便に乗務することになり、深夜から早朝にかけての子供の預け先が見つからず、必死に電話をかけ続けたという話を聞き、「なんとか手助けできないか」と考えました。その切実な想いが、会社の制度を活用することで、個人の善意を超えた、持続可能な「助け合いの仕組み」が始まりました。
3.取組内容
「チャイルドケアステーション(CCS)」は、ANAグループの社員が、社員同士で育児を支え合うという、ユニークで画期的な保育サポートシステムです。その根底にあるのは、同じ職場で働く仲間への信頼と、「お互い様」の精神です。この仕組みを支える「サポーター」となるのは、子育て経験のある社員や保育士などの資格を持つ社員、そしてANAのDNAを受け継ぐOG(退職者)たちです。サポーターは会社の兼業制度を活用して活動し、参加にあたっては全員が「居宅訪問型保育基礎研修」を修了することが義務付けられており、安全性と保育の質を担保しています。発足当初は現役の客室乗務員(CA)が中心でしたが、現在では地上スタッフなど様々な職種の社員がサポーターとして登録しており、その輪は着実に広がっています。事務局が、保育を必要とする社員(利用者)と、このサポーターとを繋ぐマッチングの役割を担い、特にフライト勤務など不規則なスケジュールの中で働く親たちが、安心して仕事に集中できる環境作りを目指しています。現在、利用者登録は約300名、サポーター登録は約100名にまで増加しています。
利用方法は、利便性を考慮した専用ウェブサイトから行います。利用者は希望の日時を予約するだけで、システムが条件に合うサポーターを検索します。CCSの強みは、単なる自動マッチングシステムに留まらない点です。もし希望日時に対応可能なサポーターが見つからない場合でも、事務局のスタッフが間に入り、個別に調整しながら最適なサポーターを探し出します。
もちろん、この前例のない社内サービスを軌道に乗せるまでの道のりは平坦ではありませんでした。社員発案のボトムアップな取り組みだからこそ、事業として成立させるためにはいくつもの壁を乗り越える必要がありました。企画段階では、「本当に社内に潜在的なニーズがあるのか」という根本的な問いに対して、慎重な検討を重ねました。また、利用を希望する社員とサポーター、双方の居住エリアや人数のバランスについて仮説を立ててサービスを開始したものの、利用が伸び悩んだ時期もありました。さらに、あくまで社員同士の助け合い(互助)が基本とはいえ、持続可能な運営のためには、最低限の収支を確保するという経営的な視点も不可欠でした。
現在は、サポーターと利用者の双方が満足できる新たな制度への改定に取り組んでいます。こうした一連の業務は、少人数の事務局スタッフが情熱を持って運営しています。増え続けるニーズに迅速かつ正確に対応するため、社内のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進活動で得た知見を導入し、予約管理やマッチング業務の効率化を推進。CCSは、社員の想いを起点に、進化を続けています。
4.これまでの効果と、今後の課題
「チャイルドケアステーション(CCS)」は、既存の外部サービスを模倣したものではなく、現場で働く社員たちの切実なニーズに耳を傾け、仲間同士で支え合うためにゼロから生み出された、ANAグループオリジナルの制度です。その独自性こそが、他の保育サービスでは得難い、確かな効果を生み出しています。
最も大きな成果は、利用者が感じる圧倒的な「安心感」です。利用者からは、「大切な子どもを預ける相手が、同じ会社の信頼できる仲間なので、自分も家族も心から安心して仕事に向かえます」という声が数多く寄せられています。この信頼関係に加え、サポーターであるANAグループ社員が持つホスピタリティの高さもCCSの大きな価値となっています。「お子さまに楽しい時間を過ごしてほしい」「親御さんに安心していただきたい」という、おもてなしのプロフェッショナルならではの温かい心遣いが、質の高い保育に繋がり、利用者からの感謝とポジティブなフィードバックの好循環を生んでいます。
一方で、多くの社員に支持されるサービスへと成長する中で、新たな課題も見えてきました。その一つが、利用者の潜在的なニーズの掘り起こしです。特筆すべきは、一度でもCCSを利用した社員のリピート率がほぼ100%という点です。これはサービスへの満足度の高さを雄弁に物語っていますが、裏を返せば、登録はしたものの、最初の一歩を踏み出せずにいる従業員がまだ数多く存在することも示唆しています。背景には、「子育てで他人の手を借りることに遠慮や抵抗を感じる」という、考え方があるのかもしれません。私たちの今後の重要な役割は、CCSが単なる「いざという時のためのセーフティーネット」に留まらず、保護者が自分時間を取り戻し、心にゆとりを持つために、もっと気軽に、前向きに活用できるものであると伝えていくことです。
CCSは、一人の社員の想いから始まった小さな取り組みでしたが、多くの従業員のキャリアと生活を照らす、かけがえのない存在となってほしいと考えています。これからも、サポーターが誇りを持って活動できる環境を整備することで、この「信頼の輪」をさらに大きく育てていきたいと考えています。